前回は、入庁から基礎研修までを振り返りました。今回は、管理運営部門での実務に入っていきます。
私が最初に配属されたのは、東京23区内の某税務署でした。都心部のせいか、やたらと忙しいという噂が事前に広まっており、心の準備はしていたのですが、実際に働き始めてみると、想像をやや上回る混沌がそこにはありました。
同期は“宝”か“ガチャ”か
同期は、私を含めて6人。内訳は男性4人、女性2人。管理運営部門としては同じでも、それぞれ所掌する事務は異なっていたため、朝会で顔を合わせることはあっても、そこまで密な関係にはなりませんでした。よく「振り出しの同期は一生の仲」などと言われますが、少なくとも私にとってはそうでもありませんでした。
別に仲が悪かったわけではありませんが、仕事を通じて深い信頼関係を築くには、単に同期であるということ以上に、性格や価値観の相性が重要なのだと感じました。
それよりも、1年目にどんな先輩や統括に出会うかの方が、職場環境の快適さを左右するというのが持論です。今では、国税専門官でも1年目から課税部門に配属されますが、当時は専科39期から49期までは全員が管理運営部門に振り出されていました。
新設された「管理運営部門」という試練
この管理運営部門というのが、機構改革で新設されたばかりの、言ってしまえば「実験的な部署」でした(そう言うと期別がほぼバレますが)。前例が少なく、業務の型も定まっていない。ベテランの上席ですら試行錯誤している中で、配属1年目の新人が放り込まれるわけですから、もう何をどうしたらよいかも分かりません。
その年を一言で表すなら、「国税職員人生で最もキツかった1年」でした。
誰も教えてくれない現場で
なにが一番きつかったか。それは「教えてもらえないこと」です。
もちろん、教える余裕がないほど現場が忙しかったという事情は理解していますが、とはいえ、納税証明書の作成・交付、現金の収納事務、総合窓口での対応、どれをとっても「これで合ってるのか?」と不安になる作業ばかり。それでも窓口に来られる納税者に対しては、そんな不安を顔に出すことは許されません。
窓口対応の話でいえば、対応自体は嫌いではありませんでした。むしろ、納税者と接することで自分の仕事の意味を実感できる面もありました。ただ、困ったのは、課税系統へ取り次ごうとするときに見せられる塩対応でした。電話越しに「は?何それ、管理運営で対応してよ」といった雰囲気が漂い、板挟みにされたことは一度や二度ではありません。
そんなこんなで、日々「社会人とは、こうして強くなっていくのか」と、妙に哲学的な気持ちになったものです。
人間関係も、残念ながらあまり居心地の良い環境とは言えませんでした。もちろん良い方もいらっしゃいましたが、全体として魅力的な先輩ばかりだったとは言いがたく、入庁したての私には「これが社会か」と感じさせられる日々でした。
野球大会と朝10時の「いせや」
それでも、すべてが苦い思い出かというと、そうではありません。
思い出深いのは、労働組合絡みの行事です。配属された直後に半ば自動的に加入させられたのですが、専科研修中にこっそり脱退しました。とはいえ、それ以前に参加させられた野球大会は妙に記憶に残っています。
ある日の日曜日、朝8時から開催される試合に半ば強制出場。無事に勝利を収めると、そのまま吉祥寺の「いせや」へ。朝10時から焼き鳥とビールで祝勝会。もう何の勝負だったのかもよく分かりませんが、「これが職場の団結力というやつか」と、謎の納得をした記憶があります。今思えば、こういう“昭和の残り香”のような体験も、悪くなかったのかもしれません。
教わらない環境が教えてくれたこと
そんなこんなで、1年目は混沌と混乱の中で過ぎていきました。
今となっては、このときの経験が“教わらない現場で、いかにして自分で学ぶか”という能力を鍛えてくれたように思います。誰かに教えてもらえることは有難い。でも、教えてもらえない状況でどう動くかが、その後のキャリアに大きく影響する。そう実感した1年でした。
次回は、課税部門への異動について振り返ってみようと思います。

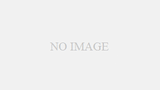
コメント