16年を振り返るシリーズの途中ではありますが、今回は少し寄り道して、先日受けてきた税理士会支部での面接調査について、備忘録的に記録しておこうと思います。
- スケジュールの記録
- 面接当日の流れ
- 面接の内容と雑談
- 面接を終えて
- 面接に備えて準備していた想定問答(供養)
- Q1. 税理士法第1条「税理士の使命」には何が定められていますか?
- Q2. 「独立した公正な立場」とはどういう意味だと考えていますか?
- Q3. 税理士の守秘義務とは何ですか?
- Q4. 名義貸しは禁止されていますが、具体的にどのような行為を指しますか?
- Q5. 広告に関して、税理士がしてはならないことは何ですか?
- Q6. 税理士が関与できない業務にはどのようなものがありますか?
- Q7. 無資格者との業務提携で禁止されていることは何ですか?
- Q8. 登録後に氏名や住所が変更された場合、どのような手続きが必要ですか?
- Q9. 税理士が業務上作成・保存すべき帳簿とは何ですか?
- Q10. 登録後、税理士として継続的に行うべき義務にはどのようなものがありますか?
- 編集後記
スケジュールの記録
まずは時系列で、登録に向けた動きを整理しておきます。
- 令和7年7月10日:国税の職場を退職
- 令和7年7月12日:税理士登録書類を税理士会に送付
- 令和7年7月14日:税理士会から申請書の受理メールを受信
- (同時に)登録手数料の振込指示を受領し、後日振込
- 令和7年7月31日:支部より面接調査の日程連絡
- 令和7年8月5日:面接調査の実施
国税職員が9月末の最短で税理士登録するには、今年は7月15日までに書類提出が必要でした。私もギリギリの日程でしたが、なんとか間に合いました。
「とりあえず書類を出して、あとは野となれ山となれ」と思いきや、数日後にはしっかり連絡があり、「8月5日に面接を実施します」とのこと。フットワークが軽いなという印象を受けました。
面接当日の流れ
当日は、10分前に会場に到着し、インターホンを押すとすぐに中に通されました。すると、面接を担当される3名の方(支部長1名、副支部長2名)はすでに揃っておられ、「お待ちしておりました」と笑顔で迎えていただきました。もともとの予定より10分前倒しで、面接がスタート。
所要時間は約30分ほど。内容は想像していたよりも和やかで、あっという間でした。
持参したものは以下のとおりです。
- 筆記用具
- 税理士試験免除決定通知書(原本)
- 名刺入れ
- 印鑑(出番はありませんでした)
「落とすための面接ではありませんから、リラックスして話してくださいね」と最初に言っていただいたおかげで、変な緊張もなく、スムーズに進んだ印象です。
面接の内容と雑談
想定問答を10個も用意して臨んだ私ですが、肩透かしを食らうくらい、税理士法の条文などには触れられませんでした。
主な内容は以下のとおりです。
- 提出書類の確認(不明点があればその場で質問)
- 税理士登録までの流れの説明
- 支部の組織構成や活動内容の紹介
- 同好会などの案内と、やや熱のこもった勧誘
幸いにも書類に不備はなく、「完璧ですね」とのお言葉をいただきました。支部長からは「早期退職の理由がよく書けていた」と、もしかしたら半分お世辞かもしれないコメントもありましたが、準備しておいてよかったなと思いました。
また、租税教室の話題にもなりました。私が直近まで法人会担当で租税教室を経験していましたので、今度は税理士として租税教室をやってみるのもいい経験になのかなとも思いました。
面接を終えて
というわけで、拍子抜けするほどスムーズかつフレンドリーな面接調査でしたが、税理士として社会に出るにあたり、いよいよカウントダウンが始まったなという実感が湧いてきた時間でもありました。
なお、実際には使わなかった想定問答集をこの後に掲載します。面接で聞かれることは人によって違うと思いますが、準備しておくことで自分の考えを整理するよい機会にはなるかもしれません。
面接に備えて準備していた想定問答(供養)
以下は、私が事前に用意していた想定問答です。ご参考までに。実際の面接では触れられなかったものの、自分の考えをまとめる上で役に立ちました。
(※各回答は、自分自身の理解に基づくものですので、使用にあたっては各自ご確認の上でご活用ください。)
Q1. 税理士法第1条「税理士の使命」には何が定められていますか?
回答案:
税理士法第1条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念に則り、納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と定められています。
私はこの使命を、単に依頼者の代理人という立場にとどまらず、社会の信頼に応える公的な役割を担っていることを意味するものと理解しています。
Q2. 「独立した公正な立場」とはどういう意味だと考えていますか?
回答案:
納税者側に立ちながらも、税務当局に迎合することなく、また過度に依頼者の要求に引きずられることなく、事実と法令に基づいた冷静な判断を行う姿勢のことだと理解しています。
税理士の信頼性は、この独立性・公正性によって支えられていると考えています。
Q3. 税理士の守秘義務とは何ですか?
回答案:
税理士法第38条により、税理士は業務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないとされています。
これは退任後も続く義務であり、依頼者との信頼関係の根幹をなす重要な規定だと考えています。
情報管理やアクセス制限の徹底、補助者への教育も含めて遵守するよう努めます。
Q4. 名義貸しは禁止されていますが、具体的にどのような行為を指しますか?
回答案:
税理士でない者に、自分の登録名義を使わせて業務をさせる行為や、登録だけして実態のない関与を行う行為が該当します。
税理士制度の根幹を揺るがす重大な違反であり、私はそのような行為には一切関与しないことを自らに誓っております。
Q5. 広告に関して、税理士がしてはならないことは何ですか?
回答案:
誇大広告や不当表示、他の税理士との比較による優越性の強調などは禁止されています。
私はホームページやSNSを活用する予定ですが、あくまで品位を損なわないよう、税理士会の倫理規定に基づいた適切な表現にとどめるよう意識します。
Q6. 税理士が関与できない業務にはどのようなものがありますか?
回答案:
弁護士や司法書士など他士業の独占業務に該当する範囲には関与できません。また、税理士法上定められた業務(税務代理・税務書類の作成・税務相談)以外の業務を、税理士業務として誤解を招く形で請け負うことも避けなければなりません。
Q7. 無資格者との業務提携で禁止されていることは何ですか?
回答案:
税理士でない者に業務を委託したり、共同事務所を構えることなどは禁止されています。
違法な営業代行やネット広告業者との連携なども注意が必要だと認識しています。
Q8. 登録後に氏名や住所が変更された場合、どのような手続きが必要ですか?
回答案:
速やかに税理士会を通じて日本税理士会連合会に対して変更届を提出する必要があります。
登録情報は公的なものですので、最新の正確な情報を維持することが義務であると認識しています。
Q9. 税理士が業務上作成・保存すべき帳簿とは何ですか?
回答案:
受任した業務の内容や報酬、顧客情報を記録した帳簿を作成・保存する義務があります。
これらは原則として5年間の保存が必要で、業務の適正性や説明責任を果たすための重要な記録だと理解しています。
Q10. 登録後、税理士として継続的に行うべき義務にはどのようなものがありますか?
回答案:
税理士会による年会費納付、36時間以上の研修受講、税理士証票の携行・保管、税理士会や支部活動への参加などがあります。
私は制度の一員としてこれらを誠実に履行し、税理士としての資質向上に努めてまいります。
編集後記
税理士登録の手続きは、書類を出して終わりではなく、こうした面接調査というリアルなやりとりを経て、ようやく現実味を帯びてくるのだと実感しました。
無事に登録が完了したあかつきには、またその記録も残しておきたいと思います。
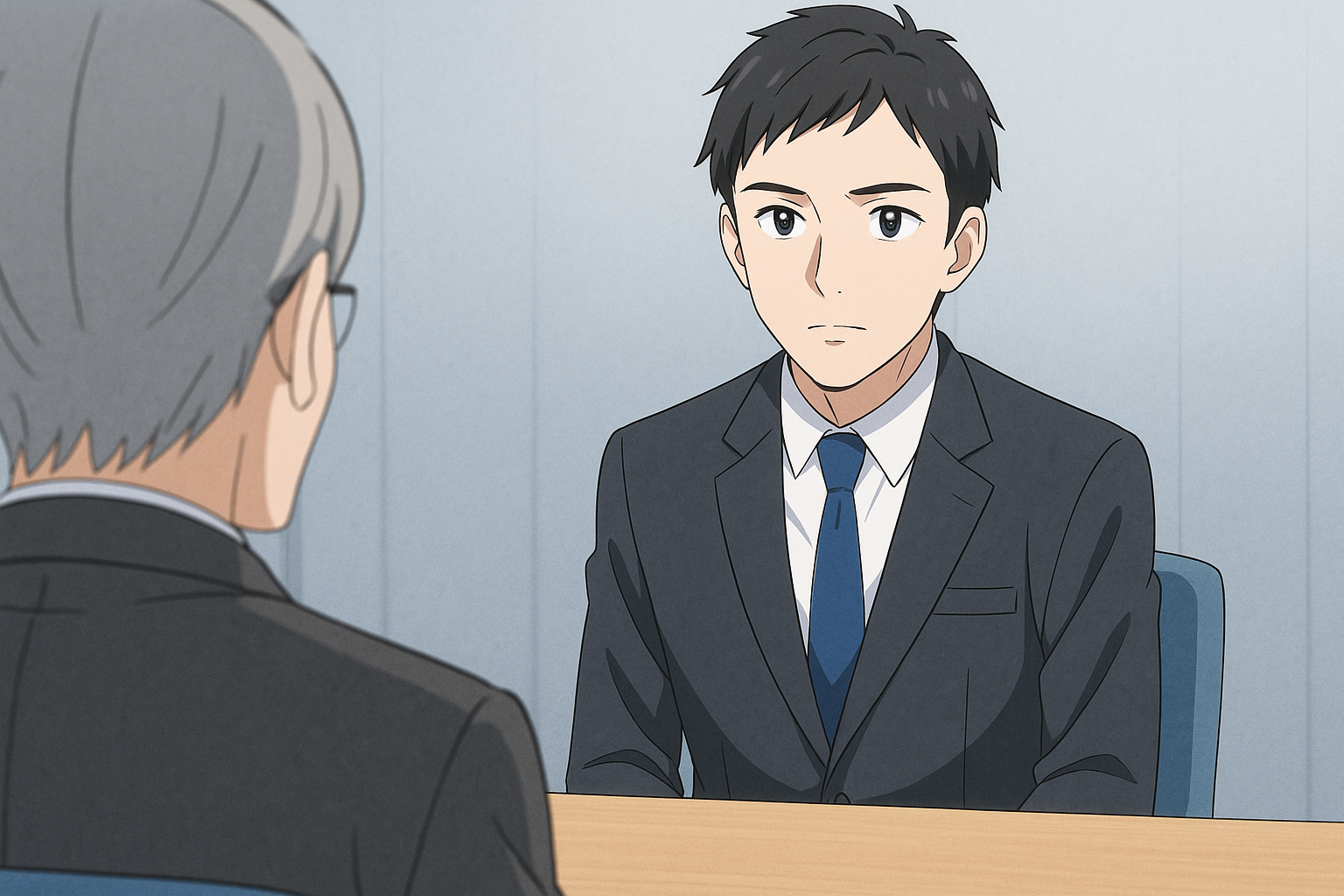
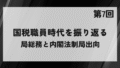
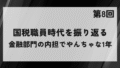
コメント