ご入庁された皆様、本当におめでとうございます。
私が入庁したのはもう十数年前になりますが、この季節になると、あのなんともいえない初々しい空気を思い出します。黒光りするスーツ、硬さの残る敬礼、妙にハキハキした返事。すべてが懐かしいです。
さて、こんな時代に、わざわざ公務員、それも国税という職場を選んだあなたに伝えたいことがあります。
変化のスピードがすべてを塗り替える時代
今は、世の中の常識や価値観が驚くほど速く変化しています。
「昔はこうだった」「これが正しい」といった話は、あっという間に通用しなくなります。過去の成功体験が、次の瞬間には“古典”になってしまう時代です。
そのため、職場の先輩や上司の「オレの時代はな…」的な語りは、参考程度に聞くのがちょうどよいでしょう。真に受けすぎると、むしろ時代に取り残される危険もあります。
「安定」の神話が崩れた今、公務員の現実を直視する
かつては「公務員=安定」という言葉が当たり前のように語られていました。私もその恩恵を受けた世代です。
しかし、今や「絶対に安全な場所」など存在しません。組織に属していても、個人で働いていても、変化への対応力がなければ生き残れない時代です。
さらに、AIの進化はその幻想を根底から揺さぶっています。
民間企業ではすでに、「新人を育てるよりAIに任せた方が早い」という判断が進んでいます。AIは議事録をまとめ、文案を作り、財務諸表を読み解き、戦略提案までこなします。しかも24時間働き、ミスも疲れもありません。
つまり、「若手を育てて戦力にする」というモデルが、民間では少しずつ終わりつつあるということです。
国税の現場にはまだ「人の仕事」が残っている
では、国税の職場はどうでしょうか。
AI活用の取り組みが進みつつあるとはいえ、調査や審理の現場で生成AIを自由に使う環境はまだ整っていません。守秘義務や端末制限の壁があるためです。
その結果、国税の現場では「人が人を育てる」仕組みが、今もなお機能しています。非効率に見える部分もありますが、裏を返せばAIでは代替しづらい「人間の手仕事」が残っているということです。
国税の文化は人間くさいものです。
たとえば「一期違えば虫けら同然」という言葉があるように、年次や序列が人間関係に影響を与える世界です。
しかしこれは、裏を返せば「人が仕事を支えている」ことの証明でもあります。AIには人間関係の機微も、空気を読む力もありません。そうした「人の世界」が、国税という職場には今も息づいています。
AI時代だからこそ、「人を育てる」価値がある
私は国税の職場で十数年を過ごし、今年度中に退職して税理士として独立します。
職場に不満がなかったわけではありませんが、「人が人を育てる」文化の中で学べたことは、今でもかけがえのない経験です。
AIが仕事を奪う時代だからこそ、人が人を育て、信頼を築くという営みはむしろ貴重です。
国税の職場は、AIではできない仕事を担う人間がまだ必要とされている場所です。
もちろん楽な仕事ではありません。けれど、せっかくこの世界に飛び込んだのですから、ここにしかない「人の仕事」の面白さを見つけてほしいと思います。
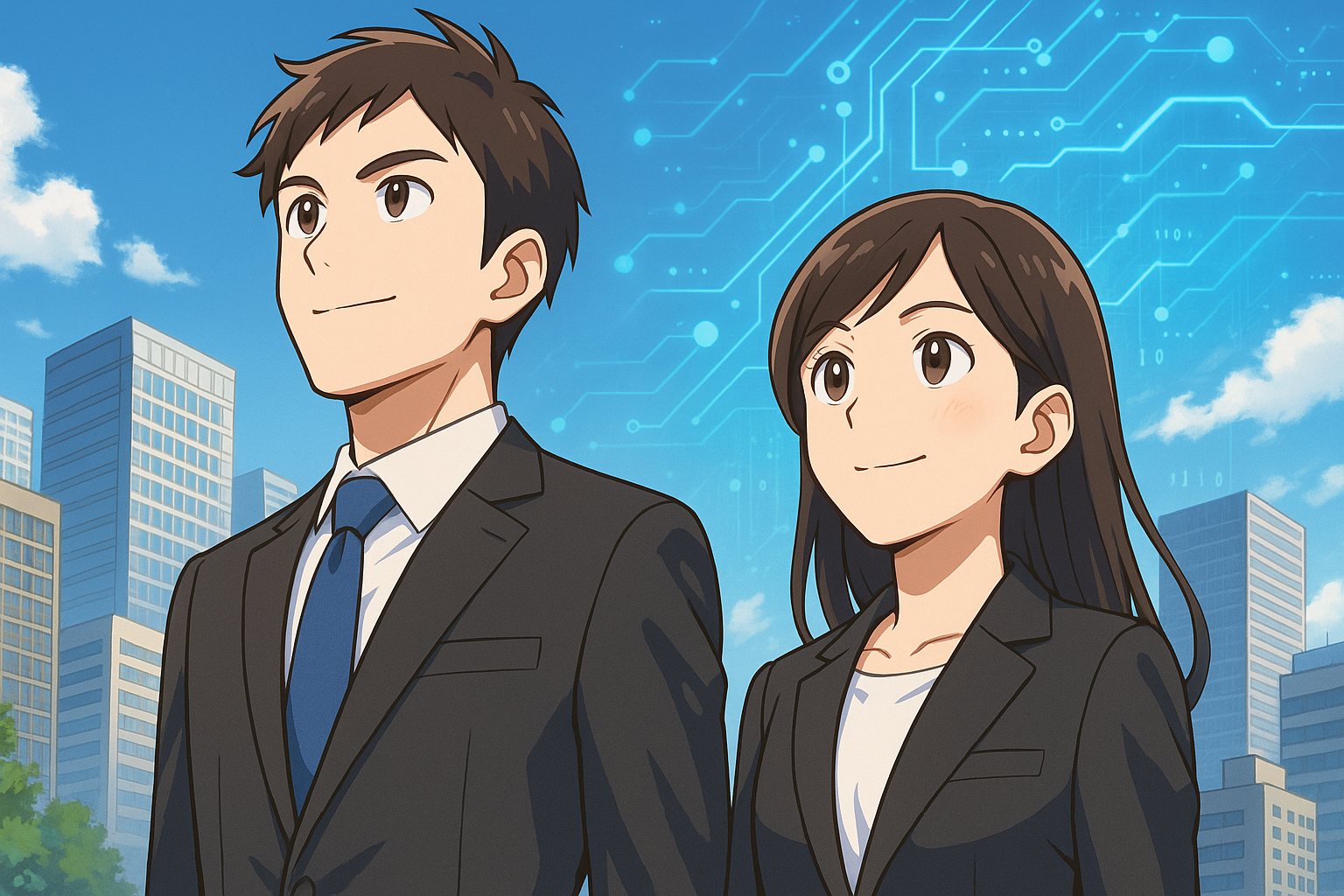

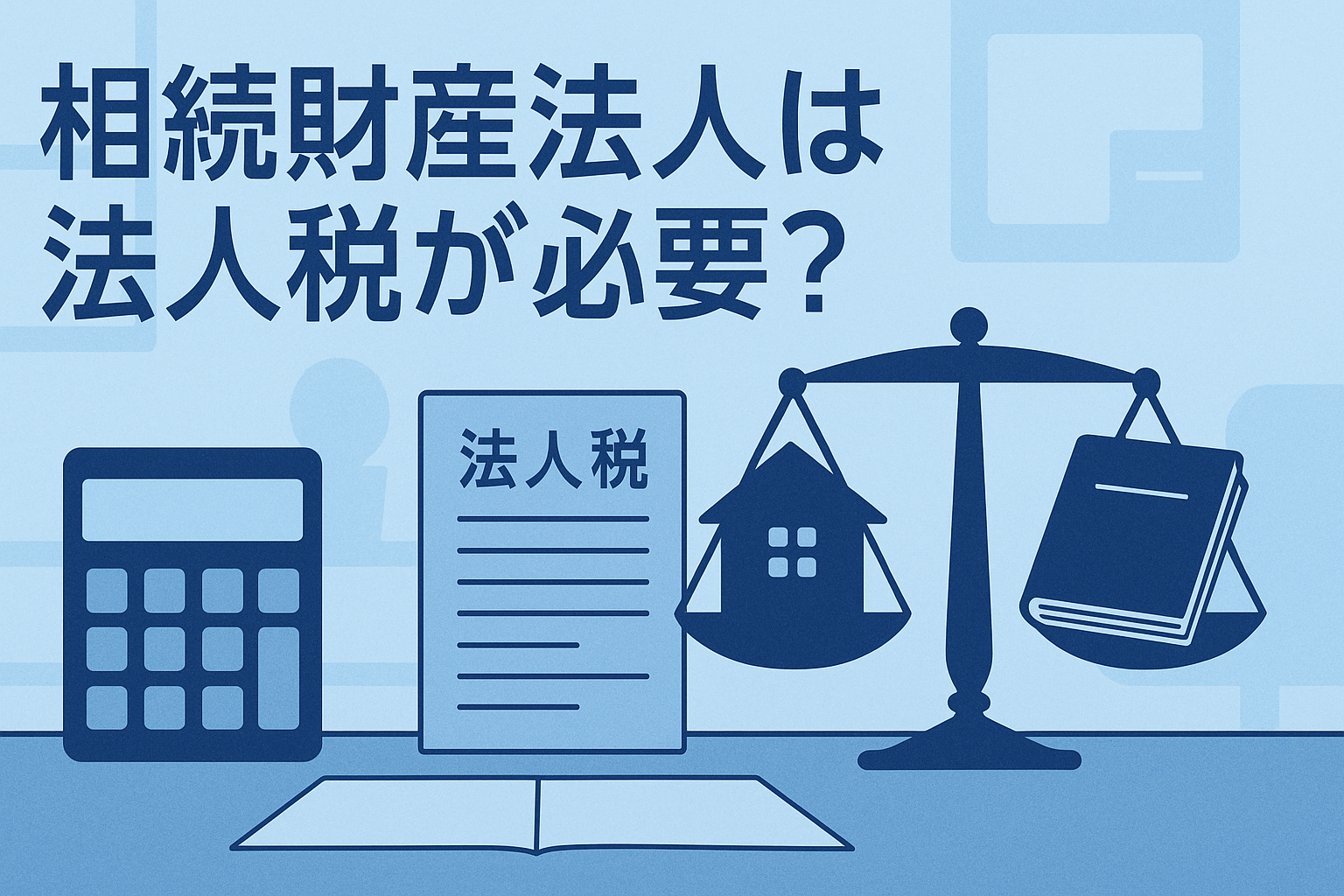
コメント