退職して数日が経ちました。
長らくお世話になった国税の職場を離れ、いよいよ個人としての活動が本格化しつつあります。が、その前に避けて通れないのが行政手続きです。
こういうの、現職のときは誰かが声をかけてくれたり、総務課が親切に案内してくれたりするのですが、いざ退職してみると、「何を、いつ、どこに」という情報は、意外と自分で探しにいかないといけません。
任意継続保険の手続きは無事に完了
まず最初にやったのは、健康保険の任意継続です。
これは現職中に人事担当者から確認があったこともあり、迷わず対応できました。私は任意継続を選び、翌年3月末まで前納することにしました。この手続きについては、別記事で既に記事にしていますので、詳細はそちらをご参照ください。
参考記事:任意継続保険の掛金案内が届いたので、計算してみた(そして支払った)
年金のことは、まるっと抜け落ちていた
さて、問題は年金です。
退職して健康保険の手続きはしても、年金のことをすっかり忘れていました。
公務員を退職したら、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)に切り替える必要があります。これ、完全に失念しておりました。
気づいたのは、昨日の夜でした。
なので今朝起きたら早速、マイナポータルから資格取得届を申請。これはオンラインで完結できたので、非常にありがたかったです。
前納制度とキャッシュレス納付を調べる
さらに調べていくと、国民年金にも前納制度があると判明。
割引が受けられるなら使わない手はありません。
ただし、これがまた一筋縄ではいきません。役所で確認したところ、
- オンラインで資格変更が完了した後、紙の申請書を年金事務所に郵送
- すぐに前納できるわけではなく、最初の数ヶ月は納付書で毎月支払い
- クレジットカードでの納付を希望するなら別途登録が必要
- 半年前納や2年前納はそれぞれ異なる時期・申請書が必要
など、情報が断片的で、ゲームのチュートリアル並みに細切れです。
私の場合、7月10日退職→資格変更完了→7〜9月は月払い→10月から半年分前納→令和8年度から2年前納という流れになりそうです。
付加年金、忘れてました
書いていて思い出しました。
付加年金、完全に忘れていました。
これ、1カ月あたり400円で、2年で元がとれると言われるアレです。FP1級の勉強で学んでいたはずなのに、現実ではやはり抜けるんですね…。
次回、役所に行くときに付加年金の申請をしてきます。
こうやって、頭の中の知識が、ようやく現実とリンクしてくるのは少し楽しい感覚でもあります。
住民税は基本「待ち」の姿勢でOK
住民税についても、多少の不安がありました。
1月1日時点の住所地が課税主体になるため、退職後すぐに何か手続きが必要かと思っていたのですが、これは概ね「放っておいても届く」とのこと。
私の場合、小金井市から府中市に転入しましたが、住民税の納付書は小金井市から府中市の住所宛に送られてくるようです。
なお、健康保険や年金のような前納制度や割引制度は住民税にはありません。そのため、一括納付のメリットもあまりなく、特別なこだわりがなければ納付書が届いてから普通に支払えば良さそうです。
年金の過去の免除分、時効で追納できず
ふと思い出して、自分の年金記録を眺めていたところ、大学生時代に「免除」扱いとなっていた期間がありました。
当時は納付猶予ではなく免除を選んでおり、その分の追納ができなくなっていることが判明。すでに10年が経過しているため、消滅時効の壁にぶち当たりました。
免除期間も年金の「受給資格期間」としてカウントはされますが、将来の年金額には影響が出ます。
もちろん、納付したからといってそれが得だったのか損だったのかは、「何年生きるか」や「制度がどう変わるか」によっても変わるので、単純な損得で語るのは難しいです。
ただ、少なくとも追納できる期間中に、自分で判断する機会があったことは確かで、その判断を怠ってしまったことにはやや反省しています。
というわけで、公務員を退職したら思った以上にやることリストがありました。
保険、年金、税金、役所……意外と人生で一番役所に通っている時期かもしれません。
でも、それもまた人生の一コマ。
新しいことをやっていると、「無職だけど学んでるぞ」という奇妙な充実感があります。気のせい?
もしこれから公務員を退職する方がいらっしゃったら、私の経験が少しでも参考になれば幸いです。

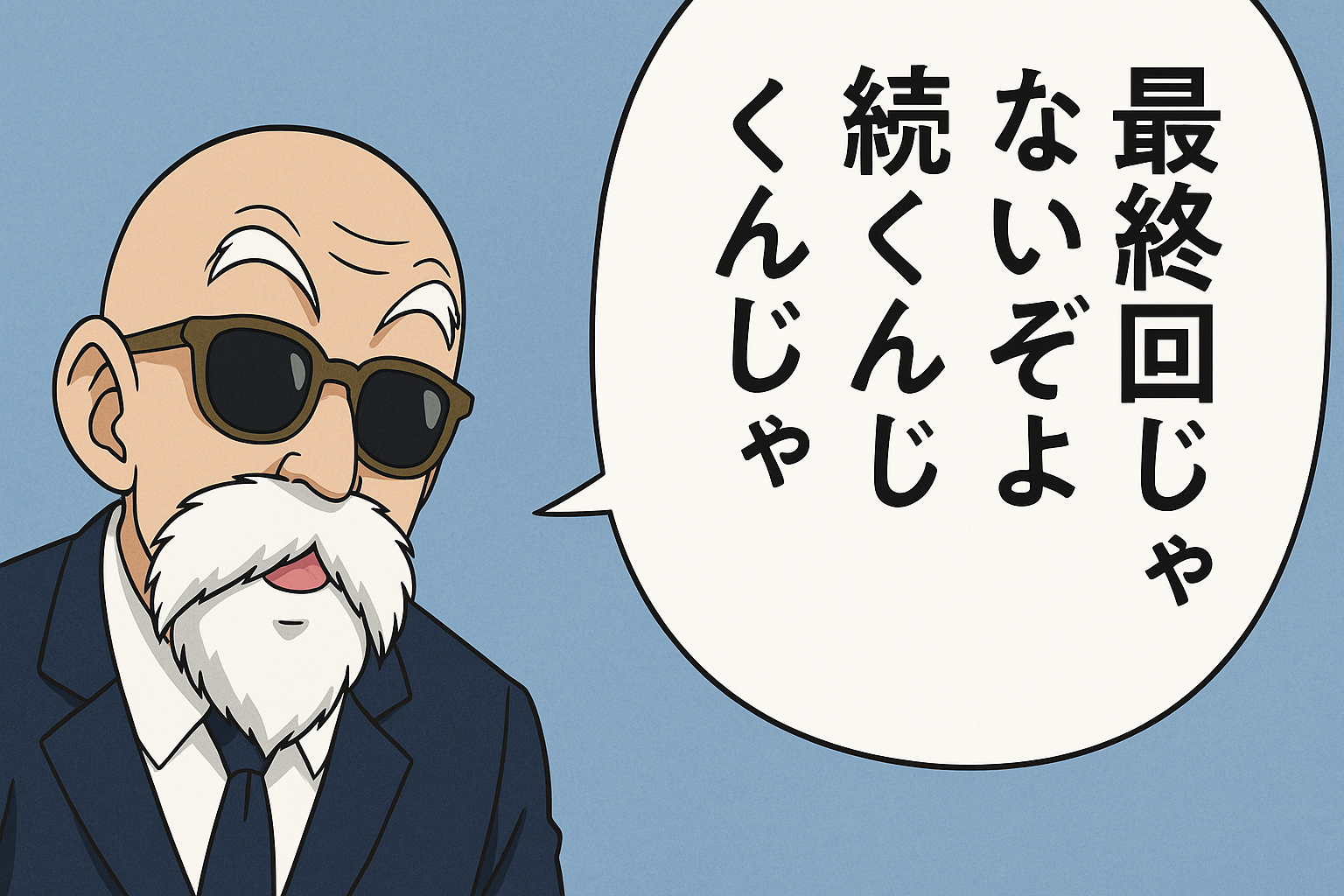

コメント