前回は、管理運営部門の1年目を振り返りました。今回はその続き、7月に異動となり、いよいよ調査畑である法人課税部門に配属されたときの話です。
異動の夏、同期の明暗
課税系統への異動先が告げられたのは7月初頭。ちょうど夏の蒸し暑さが本格化する頃でした。私を含めた同期6人の配属先は以下のとおりです。
- 個人課税部門:2名
- 法人課税部門:3名(私を含む)
- 徴収部門:1名
その内示の場で、個人課税部門に配属された女性の同期が泣いてしまったのが強く印象に残っています。彼女は法人課税部門を強く希望していたようで、本人にとってはまさに青天の霹靂だったのでしょう。人事異動というものは、希望と現実のギャップに対して時に容赦がありません。
私はというと、法人を希望していたので希望どおりではありました。とはいえ、法人じゃなきゃやってられないというほどではなく、なんとなく法人課税部門の職員が署の中で一番雰囲気良さそうだから程度で希望をしていましたが、結果的に法人を背番号とすることができてよかったと思います。
統括・上席・先輩たちに囲まれて
私が配属された法人課税部門は、7人編成でした。
- 統括官:今事務年度で60歳、まさにラストイヤー
- 上席調査官:2名
- 調査官:3期上の先輩、1期上の先輩
- 他省庁からの経験者採用者:この年が税務署での初年度
- そして私:法人課税部門デビューの若輩者
こうして並べると、私が一人だけ「新人枠」であることが際立ちます。令和の法人課税部門は統括官と事務官だけしかいないみたいなのが常態化しているため、上席が2人もいる時点で当時と今ではまるっきり違う雰囲気ですね。
調査の現場で感じた洗礼
最初のうちは、統括官に連れられて調査に同行していました。ですが正直、最初の数件は「何を調べたらいいのか」すらわかりませんでした。会計帳簿や契約書類を見せられても、どこに着目すればいいのか、どう質問を組み立てればいいのか、毎回調査先で軽くパニック状態です。
当時はまだ平成23年改正前で、国税通則法の調査手続きがいまほど厳格ではなかった時代です。たとえば、今で言う「仮決議」や「本決議」といった手続きはなく、いきなり修正申告書を添えて決議を回す、というのがごく普通でした。
月曜・火曜で調査した法人が、金曜には修正申告書を提出してくる、なんてことも。今となっては信じがたいスピード感ですが、そのおかげで1年で30件程度調査することが可能な時代でした
消費税の壁と、自分の未熟さ
この年、私がもっとも頭を抱えたのは消費税の「税抜経理方式」でした。
帳簿上の仮受消費税・仮払消費税・未払消費税の関係がよくわからず、「なぜ差額が雑益・雑損になるのか」「なぜ未払消費税というものが発生するのか」と混乱していました。
先輩や統括から仕訳がこうなるからこうだろと教えられつつ、へこみながら帰宅した日もあります。とはいえ、今となっては「1年目なんてそんなものだ」と笑って言えます。当時は「できない自分」に凹んでばかりいましたが、今思えば、できなくて当たり前の時期でした。
東日本大震災、プレハブ会場での出来事
この年を語るうえで欠かせないのが、平成23年3月11日。東日本大震災が起きた日です。
あの日、私はプレハブの申告会場で、所得税の確定申告の補助業務に従事していました。ちょうど年配の女性、いわゆる“おばあさん”の申告をお手伝いしていたところ、あの強烈な揺れが発生しました。
おばあさんはとっさに私にしがみついてきました。私も正直かなり怖かったのですが、それ以上に怖がっていたのはおばあさんの方だったのでしょう。両腕でしっかりと抱きつかれたまま、パソコンの画面がぐらぐら揺れる中、ただ立ち尽くすしかありませんでした。
この出来事を後日署内で話したところ、なぜか「私が驚いておばあさんにしがみついた」ことになっていて、一生訂正が効きませんでした。署内あるあるの伝言ゲーム、恐るべしです。
いずれにせよ、当署では被災した職員もおらず、それだけでも本当にありがたいことでした。
そんなこんなで、2年目も過ぎていく
震災の影響で、下半期はあまり調査に出られず、代わりに内観調査などに比重を置くようになりました。現場での経験が積みにくい時期でもありましたが、その分、内観調査のポイントを学ぶ機会にはなったと感じています。
こんな感じの2年目でした。次回は少し慣れてきた3年目、調査官として「自分なりのスタイル」が見えはじめた時期の話を綴りたいと思います。
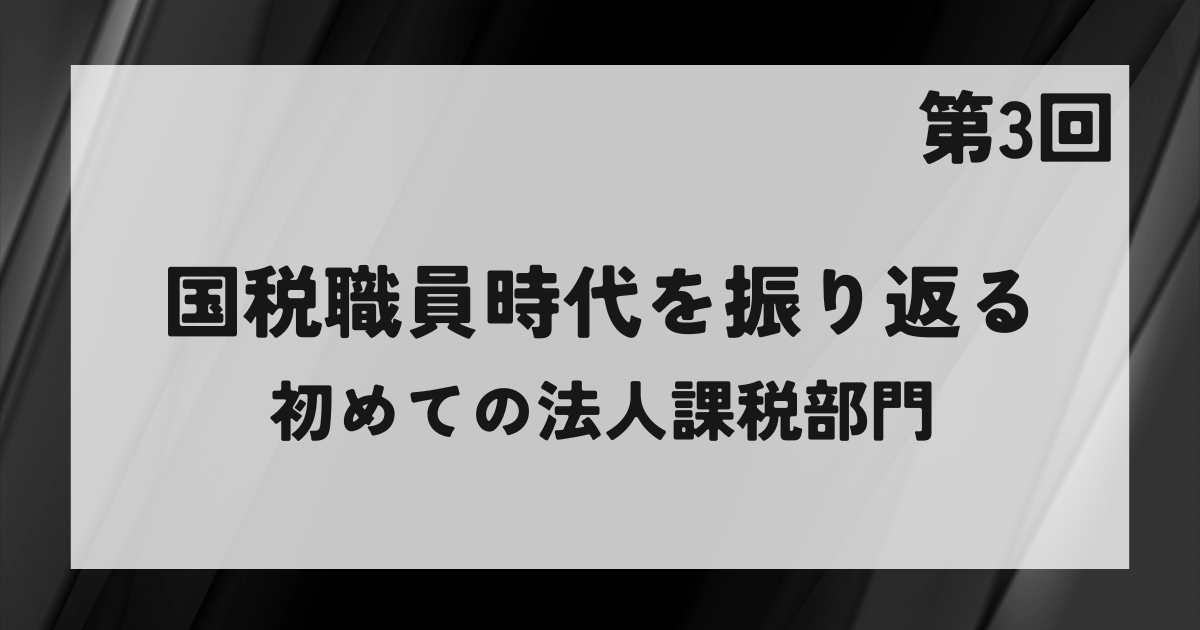
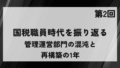
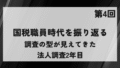
コメント