今日は会社員(給与所得者)の金融投資について、自分の公務員時代の経験を交えつつ書いてみたいと思います。
個別株からインデックス投資へ
10年ほど前までは、日本株の個別銘柄をいろいろ触っていました。業績やニュースを追いながら銘柄を選んでいくのは楽しかったものの、株価の乱高下に気持ちが揺さぶられる毎日でした。ポジションを持つだけで脳のリソースを消耗し、日々のメンタルにも良い影響はありませんでした。
そこで方向転換して、今ではインデックス投資信託一本です。きっかけは2018年、旧つみたてNISAの開始でした。年間40万円の枠を「どうせなら毎営業日積み立てにしてみよう」と思い、コツコツ投資を開始。当時は「毎日積み立てていれば相場に一喜一憂することはないだろう」と軽く考えていましたが、結果的にドルコスト平均法が効く形になり、悪くない選択だったと思います。
楽天ポイントに釣られたあの頃
2018年といえば、楽天証券がクレジットカード決済で投資信託を購入できるようになった年でもあります。月5万円まで購入でき、1%の楽天ポイントが付与される仕組み。私も例に漏れず、毎月きっちり5万円を楽天VTI(米国株式インデックス)につぎ込みました。
旧つみたてNISAはSBI証券で年間40万円、楽天証券では毎月5万円=年間60万円。合計100万円を「よし、これでコツコツ積み上げていこう」と意気込んでいました。
投資をするだけでポイントまでもらえるなんて!と小躍りしていたものの、やりすぎた結果、証券口座は気がつけば4つに増殖。SBI、楽天、マネックス、auカブコム…。ミニマリストを自称していたのにこのありさまでした。
もちろんそれぞれの証券会社から毎月1%のポイントは得られましたが、管理が大変すぎました。結局「証券口座は増やすべきではない」という真理に気づき、最終的にSBI証券に統合。マネックスとauカブコムは解約しました。楽天証券は投資商品は残していませんが、日経テレコンが便利なので新聞閲覧用に残しています。
コロナショック
インデックス投資を始めた3年目の2020年、コロナショックがやってきました。株価が急落し、含み益はすべて消え去りましてマイ転、証券口座は怖くてログインできませんでした。
そのときに思い出したのが「長期・積立・分散」の原則でした。頭ではわかっていても、実際にマイナスを突きつけられると心は揺れます。毎朝証券会社のアプリを開いては「いや、自分は積み立てているんだぞ。長期投資なんだから売っちゃいけない」と自分を励まし続けました。
あのときに売らなかったことが、今の投資方針を支える大きな財産になっています。
妻と似た投資方針
ありがたいことに、妻も似たスタンスを持っています。結婚前から米国株インデックスに積立投資をしており、山崎元さんの著書を読んで「長期・分散・積立」の投資を始めたそうです。
夫婦で投資方針が一致していると家計管理はとても楽です。「暴落しても積み立て続ける」という原則を共有できるので、互いに「売らない勇気」を確認し合えます。現在はマネーフォワードで家計と投資を一括管理し、資産推移を可視化。投資は家計管理の延長線上にあることを実感しています。とはいえ、日々の資産額の上下に惑わされすぎないよう気を付けています。
バイ&ホールド、そしてバイ&フォゲット
今では為替や株価に一喜一憂することはなくなりました。私と妻の投資方針は「buy & forget」です。買ったら忘れる。積み立てたら放っておく。
新NISAが始まり、非課税枠も拡大しました。私たちはその枠を淡々と埋めていく日々です。資産運用を特別な勝負事にせず、生活の一部として自然に続けることが重要だと感じています。
会社員のインフレヘッジとしての金融投資
会社員にとっての金融投資の意味をひとつ挙げるとすれば「インフレヘッジ」です。給与はそう簡単に上がらない一方で、物価はじわじわと上がっていきます。銀行に預けていても利息はほとんどつきません。
そこで有効なのが、株式インデックスなどへの長期投資です。もちろん短期的な値動きはありますが、長期で見れば企業の成長や経済の拡大に連動して資産は増えていきます。給与所得者にとって投資は資産を殖やす手段であると同時に将来の購買力を守る手段でもあると考えます。
おわりに
こうして振り返ると、私の投資遍歴は「ポイントに釣られて迷走し、暴落で自分を励まし、妻と足並みをそろえながら落ち着いていった」という流れでした。
会社員にとって金融投資は、給料を何倍にも増やすギャンブルではなく、生活を支えるインフラみたいなものだと思います。毎月の積立を続け、NISAをうまく活用することで、未来の安心感を少しずつ積み上げていけるのだと思います。

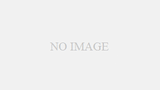
コメント