私は今年、公務員を退職して個人事業主(税理士)として独立する道を選びました。退職に伴い、健康保険や年金の手続きは当然として、ふと頭をよぎったのが「そういえば、iDeCoはどうなるんだ?」という疑問です。
公務員時代には、給料天引きでiDeCoに拠出していました。最初は月額12,000円でしたが、2024年12月から公務員の掛金上限が20,000円に引き上げられたため、私もそれに合わせて拠出額を変更しました。掛金よりも「毎月171円の手数料」が気に食わないところでしたが、所得控除のメリットが効いてくる年収レンジではあったので、公務員にも導入された初年度の2017年からやっています。
退職すると掛金はどうなる?
結論からいえば、退職して給与からの天引きが止まると、自動的に「運用指図者」という状態になります。要するに、もう掛金は入らないけれど、積み立てた資産はそのまま運用され続けるという状態です。
私はSBI証券を通じてiDeCoを利用していました。公務員時代は、掛金の中から国民年金基金連合会への手数料105円と、信託銀行の管理手数料66円、合計171円が差し引かれていました。退職して掛金をやめると、このうち国民年金基金連合会への手数料は不要になり、残るのは信託銀行の月66円だけ。
つまり「掛金をしなくても資産はそのまま投資信託で運用され続けるし、毎月のコストは66円に下がる」ということです。
売却されるわけではない
ここで誤解しやすいのが「掛金が止まったら資産は現金化されてしまうのか?」という不安です。私も一瞬そう思いました。しかし実際はそんなことはなく、これまで積み立ててきた投資信託はそのまま市場で運用が続きます。
私の口座でいえば、これまでの拠出額が1,310,453円。運用益が1,211,719円で、令和7年9月現在の評価額は2,522,172円になっています。積み立ての倍近い含み益です。これを現金にされて60歳までロックされるなんてことを想像していましたが、実際は引き続きS&P500の波に乗れる状態です。インフレヘッジの観点からも安心しました。
個人事業主になると掛金枠が広がる
公務員時代の掛金上限は、長らく月12,000円でしたが、2024年12月から20,000円に拡大されました。それでもなお、個人事業主になった後の上限はケタ違いです。現在は月68,000円ですが、さらに制度改正が予定されており、月75,000円まで拡大される見込みです。
税理士として事業が軌道に乗れば、掛金を増やすことで所得控除の効果が大きくなり、節税メリットを享受できます。とはいえ、私はすぐには拠出を再開する予定はありません。まずはNISAの非課税枠(生涯1,800万円)を埋めることを優先し、その上でさらに余裕があれば、iDeCoの掛金を再開していくつもりです。
制度を使う側の視点
iDeCoの概要を勉強した際は、60歳まで公務員として働き続けるつもりでしたので、60歳まで引き出せないことに関しては何も思っていませんでしたが、退職して個人事業主となった今では、資金拘束のリスクをより感じます。だからこそiDeCoはNISAなどと組み合わせて全体の資産バランスを考えていく必要があるのかもしれません。
退職後にわかったこと
今回、自分が退職してiDeCoを見直したことで、
- 掛金をやめても資産はそのまま運用される
- 手数料は月66円に下がる
- 引き出しはできないが、投資信託は複利で働き続ける
- 独立すれば掛金枠が6.8万円(将来的には7.5万円)に広がる
といった点を確認できました。制度の説明だけを聞いていた頃よりも、肌感覚で理解できた気がします。


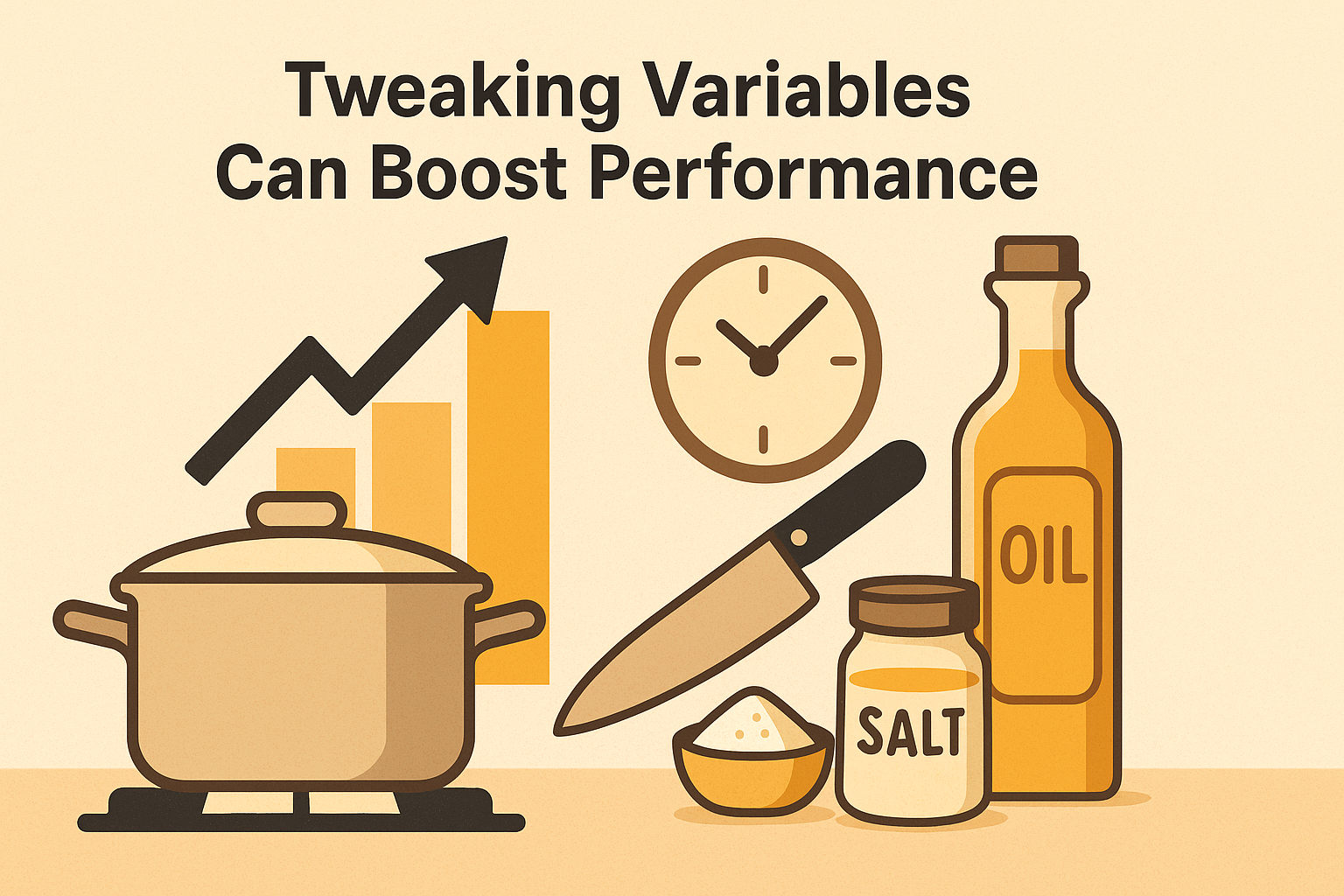
コメント