個人事業主は、サラリーマンと異なり「誰も守ってくれない」世界にいます。
毎月の給料もなければ、仕事を取ってくるのも自分。
だからこそ、つい「自分を高めること」そのものを目的化してしまうことがあるような気がします。
本を読んで、セミナーに出て、自己分析をして…。
それ自体は前向きな活動のはずなのに、
気づけば「自己啓発」や「インプット」ばかりが進み、肝心の行動が止まっている。
最近の自分を振り返っても、まさにその傾向があると感じました。
「勉強してる感」が一番の罠
個人事業主にとって、勉強は仕事の延長です。
新しい知識を得ること自体が楽しく、しかも「自分の将来に投資している」という正当化ができる。
でもその投資が、本当にリターンを生む内容なのか?という点を、つい見落としがちです。
たとえば最近よく耳にする「生成AIで業務を効率化」もその一例。
確かに、AIを使えば会計処理や文章作成などが合理化できます。
ただ、それを学ぶこと自体が直接売上につながるとは限らない。
「AIを使える税理士」というブランドを作れるのは、
それを武器にクライアントを獲得してからの話です。
合理化の研究も、自己啓発も、自己分析も、どれも大切。
でも、事業の中心軸が「稼ぐ」「提供する」「感謝される」から離れすぎると、
それはただの知識のコレクションになってしまいます。
税務署時代にもあった「知識の聖域化」
組織の中でも似たような現象はありました。
税務署勤務時代、税法の理論や調査手法にやたら詳しい職員がいました。
「租税法体系の構造」や「海外税制の比較」など、話している内容は立派です。
でも、実際の調査現場では納税者と向き合えず、数字の裏を読めない。
逆に、現場感覚のある調査官は理屈よりも行動が早く、
結果として案件を早期に終結させていました。
知識を深めること自体は悪くありません。
ただ、知識を得た“先”で何をするのかが重要です。
税法でもビジネスでも、「行動を伴わない理解」は、理解していないのと同じだと今は思います。
自己分析も、やりすぎると「自己満足」になる
近年は「自己理解」「ストレングスファインダー」「16タイプ診断」など、
自分を客観的に見つめ直すツールがあふれています。
ただ、それをやったからといって仕事の成果が劇的に上がるわけではありません。
「自分は分析タイプだから営業は向かない」と分かっても、
誰かが代わりに売上を作ってくれるわけではないのです。
自己分析に時間とお金をかけると、不思議と納得感があります。
「ああ、今日はちゃんと自分と向き合った」と思える。
でも冷静に見れば、それは向き合った気分に過ぎないことも多い。
自己分析は手段であり、結果を出すためのスタート地点にすぎません。
結局、行動に移さなければ、どんな分析も「思考の自己満足」で終わります。
それがわかっていても、私自身、気を抜くとすぐにそちら側に引き込まれる。
だからこそ「自戒」として、こうして文章にしています。
「やらないよりやったほうがいい」領域の落とし穴
自己啓発や読書、セミナー参加などは、
一見するとどれも“やらないよりやったほうがいいこと”に見えます。
でも、その言葉に安心して、永遠に準備段階を歩き続ける人が少なくありません。
やる気が出ない時ほど、私たちは“勉強している自分”に逃げがちです。
勉強している間は、リスクがない。
失敗も批判もされずに、成長している気分を味わえるからです。
しかし、ビジネスは行動して初めて現実が動く世界です。
試して、反応を見て、修正して、また挑戦する。
その繰り返しの中でしか、自己啓発の成果は“お金”や“信頼”という形になりません。
行動があってこそ、インプットが活きる
生成AIの知識を得たなら、実際にそれを使って請求書を作ってみる、
記事を書く、顧客対応に活かしてみる。
自己分析で得た強みを知ったなら、それを基に営業のスタイルを変えてみる。
そうして初めて、学びが実学になるのかと思います。
行動してこそ、自己理解は深まる
自己投資を続けるのは大切ですが、
それが“行動しない自分への免罪符”になってしまうと、本末転倒です。
稼げるかどうかは、知識の量ではなく試行の回数で決まる。
学びは常に、現実のアクションプランとセットで完結するものだと肝に銘じておきたいものです。
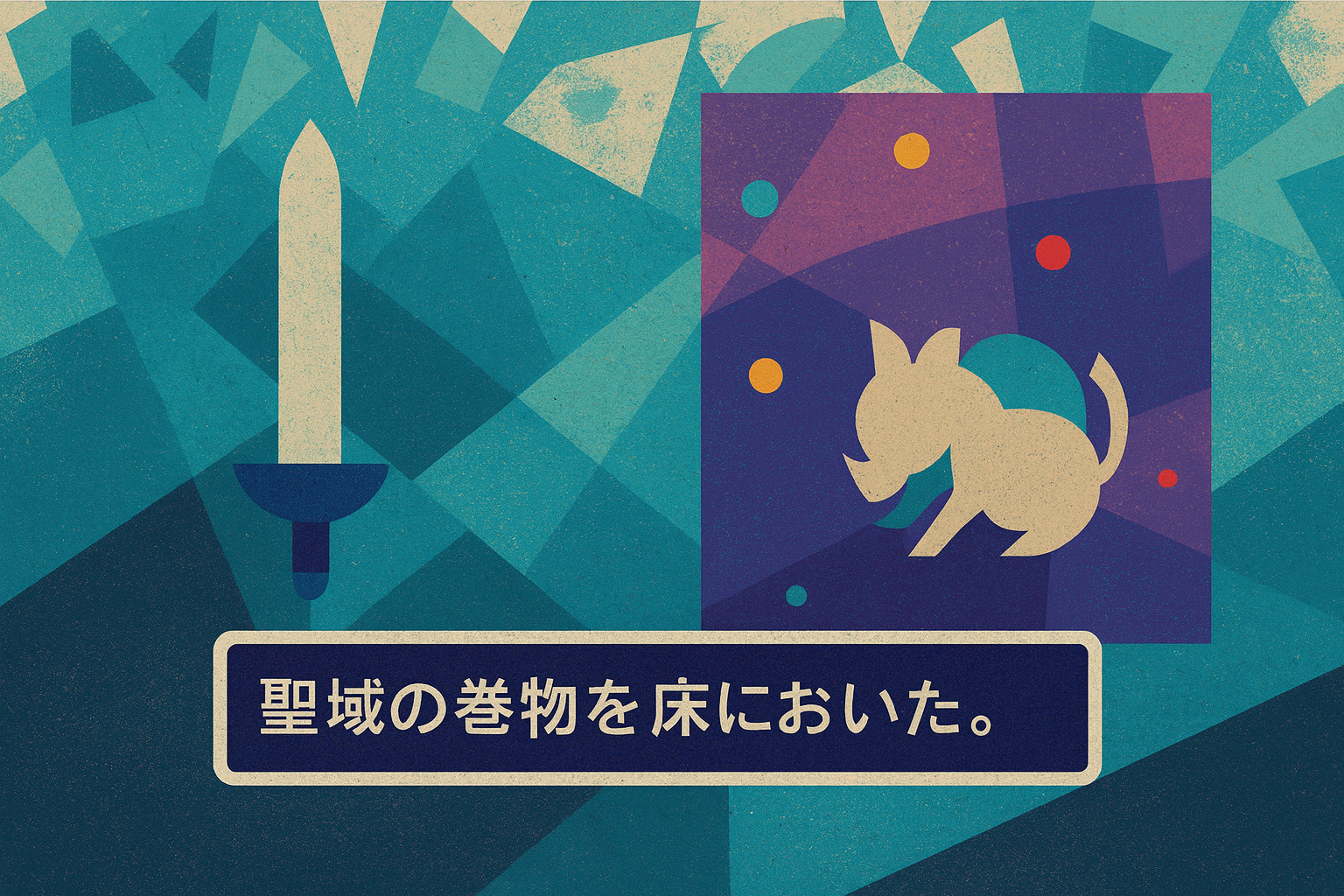
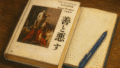
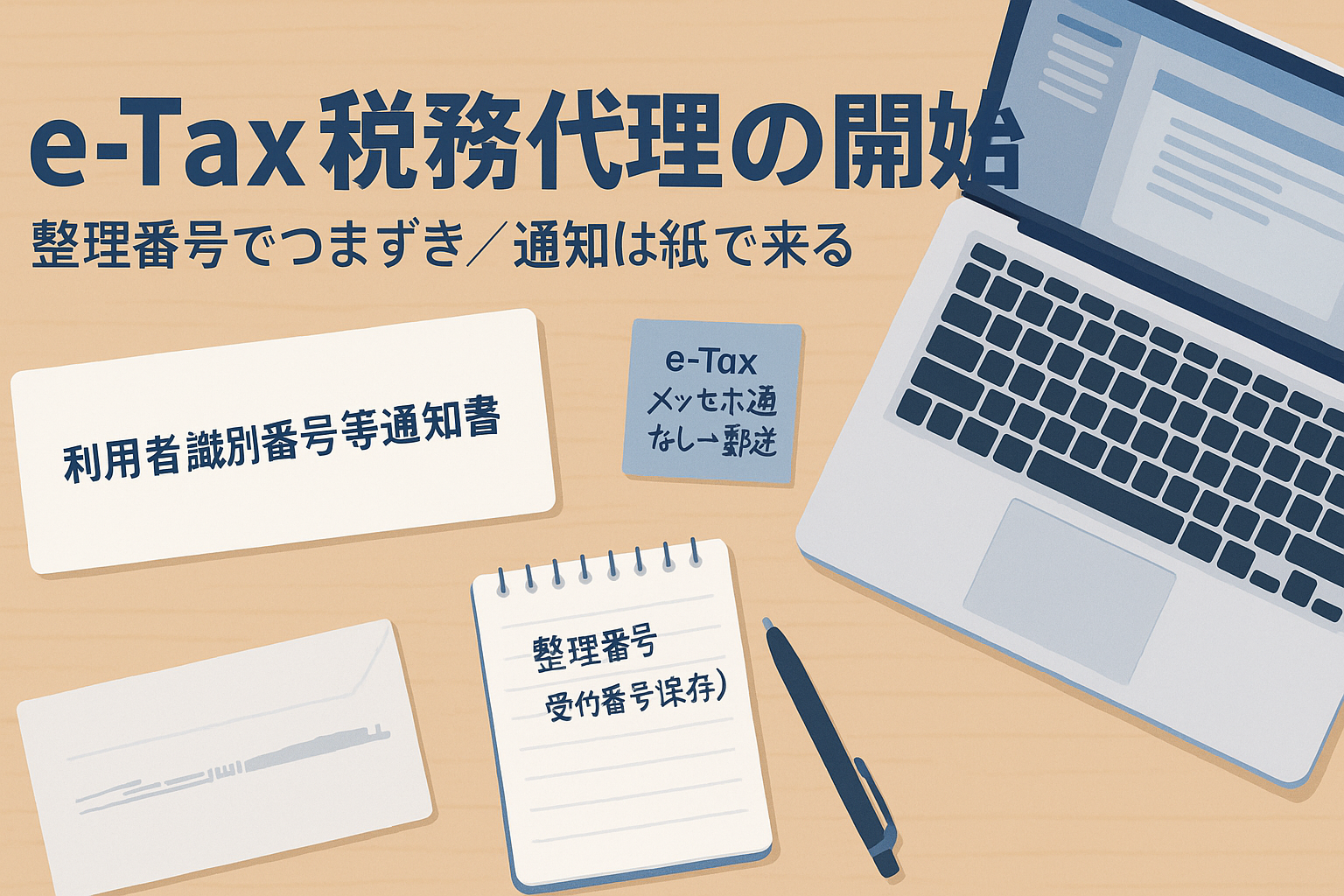
コメント