最近はルミエール府中で本を借りることが多いのですが、今回はちゃんと本屋で買いました。レジに持っていく前に、まず値段を二度見。フルカラーで約550ページあって、税抜1,780円。この分厚さでこの価格は正直破格です。
著者はYouTubeでおなじみの両学長。動画で伝えている内容は、税理士として見ても筋が通っています。家計の基本、投資の原則、保険の考え方——どれも“ネットの早口言葉”ではなく、制度と数字の土台に立っている。だからこそ、「本としてまとまったらどうなるんだろう」と気になっていました。
物語形式なのに、大人の学び直しに効く
物語は、小学生のソータが異世界に飛ばされ、メグという少女と一緒に「お金の5つの力」を鍛える旅に出る、というもの。装いは児童書ですが、読むほどに“大人の学び直し”として機能します。図解が多く、話がすっと頭に入る。疲れた日でも読み進められる軽さがあります。
登場人物がそれぞれ、現実にも必ずいるタイプの象徴になっているのが面白い。たとえばクロート。投資の腕はシロート寄りなのに、友達が多くて、ソータとメグのお店(サービス)を周囲に広めてきちんと他者貢献をしている。こういう人、実際の商売で本当に頼りになりますよね。数字の知識ばかりでお客さまに届かないより、まず人を連れてきてくれる人の価値は大きい。
もう一人、ケンヤが印象に残りました。裕福な家庭に育ち、新作ゲームや流行のおもちゃを持っている。一見、鼻につくキャラクターに見えますが、彼自身は嫌味がない。動画配信で自分なりに稼ぐし、ペットボトルロケットで遊ぶときはソータをちゃんと誘う。私の経験でも、お金持ちの家庭の子どもが傲慢ということはありません。むしろ親の教育が良くて、フラットでオープンな子が多い。ケンヤにはそういう空気があり、物語に現実味を与えています。
「5つの力」は順番と重み付けが命
本筋の「5つの力」は、稼ぐ・守る・使う・増やす・貯める。どれも聞き慣れた言葉ですが、順番と重み付けが大事だと再確認しました。稼ぐ→貯める→増やす…その過程の中で必要になってくる、守る、使う。この図式ですね。
物語の途中で、ソータが怪しい儲け話に引っかかりかける場面があります。“すぐ・楽に・大きく”は、いつの時代も危険なキーワードです。一方でメグは、必要以上の保険に入ろうとしがち。ここもまた現実そのまま。心配性が悪いわけではなく、仕組みを知らないと「安心の買いすぎ」になる。いずれも、現実社会で多く観測される事象だなと思います。
読んだあと、手を動かしたくなる
正しい情報は、感情を落ち着かせてくれます。「やることは分かっているけれど腰が重い」——そんな課題に、行動のきっかけを与えてくれるのもこの本の良さ。難しい金融用語を並べるではなく、平易で惹き込まれるストーリーで背中を押す力がある。
価格についてもう一度。フルカラーでこのボリュームなら、親子で共有して何度も開く前提で作られているのだと思います。大人が一読して終わり、ではもったいない。例えば、家族会議の日に「今日は第○話を読んでみよう」と決める。子どもがいない家庭でも、パートナーと読むと、自然に話題が具体化しそうです。「うちの保険、どうなってたっけ?」といった感じでしょうか。
税理士目線でも“安心して勧められる”
税理士としては、内容の“安心感”も推したいところです。投資は長期・分散・低コストが軸。保険は“めったに起きないが起きたら困る”事象だけ。ネットには刺激的な情報があふれますが、結局はこういう基本が強い。
読後、自宅兼事務所の家賃の引き落とし口座を事業用口座から生活用口座に変更しました。やったほうがいいなと思っていたけど、ネット上でサクッと変更できたのでさっさとやっておけばよかった。こういう“手触りのある行動”に変換しやすいのが、この本のいちばんの効用かもしれません。
総じて、子どもに読んでほしいのはもちろん、大人にも刺さる一冊でした。物語の登場人物を「身の回りの誰か」に置き換えながら読むと、気づきが増えます。現実の世界でも、そういう人たちと関わりながら、自分の5つの力を少しずつ鍛えていけたらいい。
気になっている方は、まずは本屋で手に取って、数ページめくってみてください。紙の厚みと色の多さにちょっと驚き、読み進めるうちに、日常の使い方がいくつも思い浮かぶと思います。とてもおすすめ。
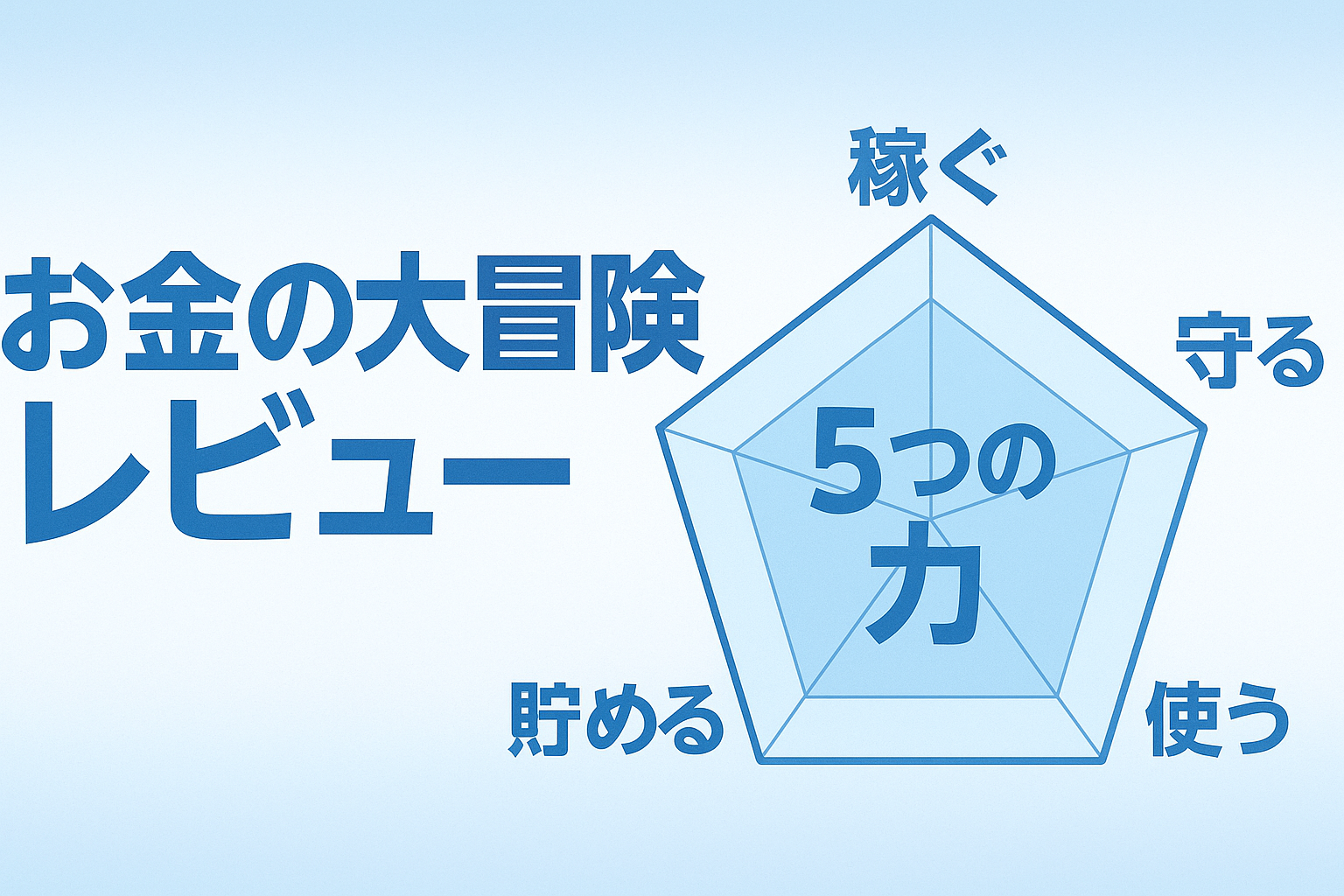
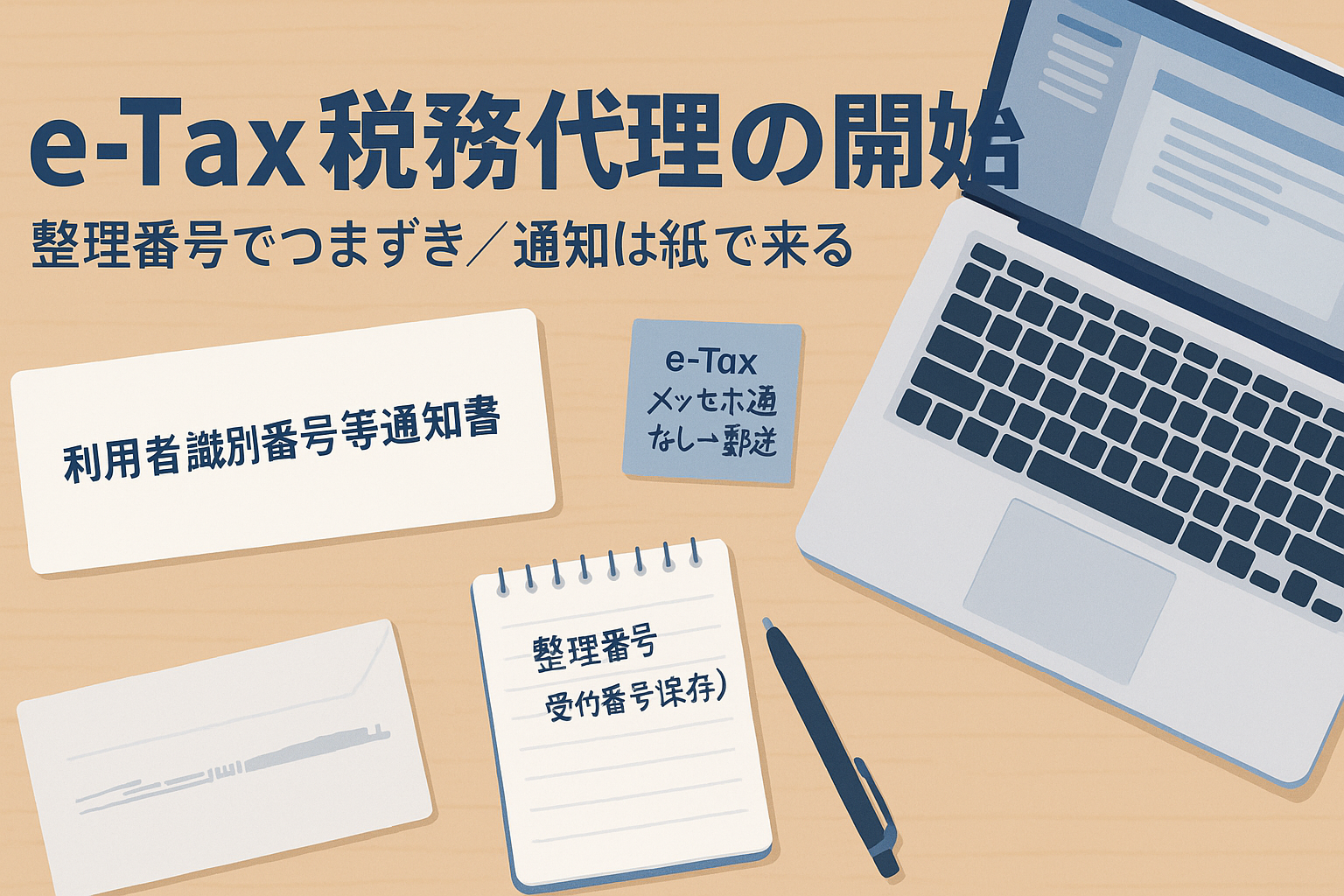

コメント