独立してから、明らかにスマホを見る時間が減りました。
最近ふとスクリーンタイムを確認してみたところ、一日の平均使用時間が2時間を切っていました。
もちろん「それでも多いのでは?」という方もいるかもしれませんが、私にとってはかなり大きな変化です。
勤めていたころは、通勤時間の帰り道でSNSを開くのがルーティンになっていました。
国税時代は電車に乗ると、無意識にX(旧Twitter)やYoutubeを開いていたものですが、いま思うと、あれはただ単に手持ち無沙汰なだけだったように思います。
PCが主役になった結果、スマホが子機になった
独立後は自宅兼事務所で作業する時間が増え、スマートフォンの役割はすっかり“PCの子機”になりました。
仕事はほぼパソコンで完結しますし、情報収集も書き物も何もかもPCのほうが速い。
そうなると、スマホの小さな画面を見る必然性は減っていきます。
もちろん、パソコンでSNSばかり眺めていては本末転倒なので、PCのブックマークにもSNSを置かないという自己ルールを決めています。
SNSがワンクリックで開ける環境は、想像以上に危ない気がします。
ドーパミンが吹き出して、仕事のクリエイティブな集中を奪っていきます。
やっぱりドーパミンを生むなら、仕事そのものから得るのが一番だと思います。
Xのリロードは「スロット」である
ところで、スマホでXをリロードするときのUIは、カジノのスロットマシーンと同じ原理だという話をどこかで聞いたことがあります。
画面を引っ張って離すと、新しい情報がガチャッと出てくる。
これが脳の報酬系をいたく刺激して、ついついリロードを繰り返してしまう。
自分の意思とは関係なく、設計そのものが依存を生むようにつくられているのだから、気をつけるのは当然です。
そして、気をつけないと本当にいくらでも時間を取られる。
SNSは無料ではなく、「時間を貨幣として支払うタイプの有料サービス」だと意識しておくべきだと思います。
オルタナティブな依存先
散々語られてきたテーマかもしれませんが、何かの依存を減らすには代わりの依存先を持つことが大事です。
私の場合、ゲームだったり(これもドーパミン中毒になる危険はありますが、SNSやYouTubeショートよりは予後が良い気がします)、読書だったり、筋トレだったり、家族との時間だったり。
結局、人間は“何かに熱中していない時間”に、手っ取り早く気持ちよくなれるものへ流されてしまうのだと思います。
依存は悪いことではなく、選び方の問題
“依存”と聞くと否定的なイメージが湧きますが、本来はただの傾向であって善悪ではありません。
大事なのは、何に依存するか。
スマホではなく、自分の人生を良くしてくれる方向に依存先を選べればいいと思うんですが、それができれば苦労しないという話ではあります。
手っ取り早く脳の報酬系を刺激する安易な手段に頼るのではなく、中長期的に大きな報酬につながることに時間を投下していきたいものです。
時間軸は、できる限り長期で考えていきたいですね。
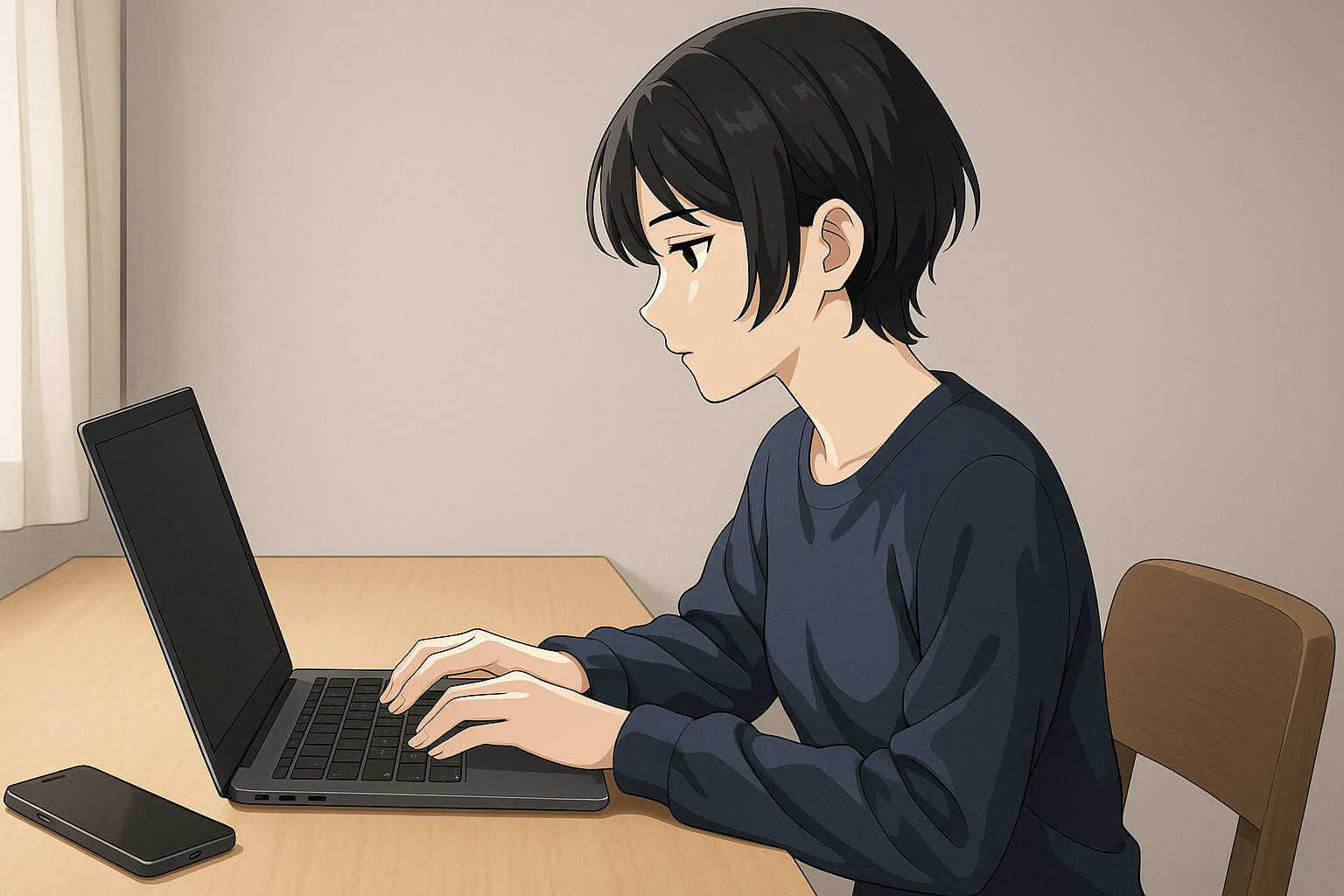
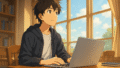

コメント