机の上で勉強を毎日続ければ、資格試験には受かる。
実際、国税職員になるための試験は、まさに机の上でのお勉強の結晶です。筆記試験で合格点を取り、形式的な面接を通過する。それで職員として採用されるわけですから、「机上の勉強こそが人生を開く」という成功体験が骨の髄まで染み込みます。そうなると、当然ながら勤め人気質にもなりやすい。
ところが社会に出てみると、この「机上の勉強=人生攻略の全て」という図式が、資本主義という大きなゲーム盤の上では心もとないことに気づきます。机の上では勝っていたはずなのに、気づけば別ルールの試合会場に立たされていた──そんな感覚です。
「宅建より物件」という現実
不動産の世界には「宅建より物件」という言葉があります。宅建士の資格が必要な場面はもちろんあります。重要事項説明などは資格者でなければできません。しかし、入居希望者にとって重要なのは「この物件に住みたいかどうか」であって、大家が宅建を持っているかどうかではない。
これは不動産業界だけの話ではなく、資格ビジネス全般に通じる真理だと感じます。私が歩んできた税務の世界でも同じです。税理士資格は独占資格ですから、登録がなければ税務代理はできません。しかし「資格があるから仕事が降ってくる」なんてことは起きません。そこに待っているのは、資本主義の冷ややかな現実です。
難関資格がメシを食わせるのか?
「難関資格がメシ食わせてくれるのとちゃいまっせ!」
──私の中のなにわの商人がそう叫びます。
資格そのものは武器であり、入口の鍵であることは間違いありません。社員税理士として勤めに出れば、安定した収入を得ることは可能です。しかし、独立という選択肢をとる以上、資格はスタート地点でしかありません。
資本主義の荒波に放り出されたとき、必要になるのは「勉強で得た知識」よりも「どうお金を回すか」「どう人に価値を伝えるか」という経営と営業の感覚です。ここを見誤ると、「資格は取ったけれど食えない」という現実に直面しそうな気がします。
「資格の檻」に囚われる人たち
机の上の勉強を極めた人ほど、資格に守られている感覚に安住しがちです。私も税理士登録前の身で言うのはおこがましいですが、士業資格を手にしたことで逆に身動きがとれなくなっている人を見てきました。
以前読んだ『税理士ならだれでも年収3,000万』という書籍でも、このあたりが鋭く指摘されていた気がします。
参考記事:『税理士ならだれでも年収3,000万円』を読んで、目が覚めました(物理的にも)
要は「資格の殻にこもるな、経営の視点を持て。士業に安住している人が多いからこそ、経営や営業にも踏み込めば差別化は容易だ」という内容です。
あの本を読み終えたとき、机の上での勉強に偏りすぎることのリスクを改めて痛感しました。
勉強と資本主義のズレ
机の上での勉強は、閉じられた世界のルールを理解するためには役立ちます。試験範囲は有限で、努力した分だけ結果がついてきます。ところが、資本主義社会のルールは無限に広がり、しかもルール自体が頻繁に書き換えられます。
勉強すればするほど「安心感」を得られる一方で、社会では「動いてなんぼ」「試してなんぼ」という不確実性を生き抜くスキルが必要です。机の上での努力が、資本主義の荒波においては足かせになることすらある。このギャップは、勉強好きな人ほど見落としやすい落とし穴ではないでしょうか。
私自身のジレンマ
国税職員として16年3か月を過ごした私も、このジレンマと無縁ではありません。採用試験から始まり、毎年の研修、税法の条文の読み込み。すべて「机の上でのお勉強」の延長線上にありました。その成功体験は確かに私を支えてきましたが、同時に「勤め人としてのレールの上」を歩む発想から抜け出すのを難しくしていたように思います。
独立を目の前にした今になってようやく、「勉強」だけでは食えない、「資本主義ゲームのルール」を学び直す必要があると痛感しています。
資本主義を生き抜く勉強とは
では、これからの私が机の上でやるべき勉強は何か。
それは「経営を学ぶこと」「営業を学ぶこと」「人に伝える技術を磨くこと」だと考えています。
机の上で法律や条文を暗記するのも必要ですが、それ以上に「人と会う」「お金の流れを読む」「自分の価値を市場にどう提示するか」を実地で学ぶ必要があります。これこそ、資本主義社会で生き抜くための勉強だと思います。
机の上の勉強は、人生のパスポートを得るための大切な手段です。けれど、手にしたパスポートをどう使うかは、また別の話。資格はゴールではなく、ただの入場券というわけで、今後は色んなアトラクションに乗り続けていかなければならないなと思っています。

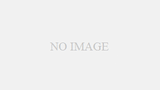
コメント