人は、学生服を着ている間は服のことなど真剣に考えません。なんせ毎日ほぼ制服。ファッションセンスの有無がバレようがない日々です。ところが、大学生や社会人になって「私服」が求められるようになると、一気に世界が変わります。
私の場合、その変化はある意味、服装の黒歴史の幕開けでもありました。
中学時代のファッション革命(と呼ぶには無理がある)
服に興味を持ち始めたのは中学2年生くらいだったでしょうか。地元のジーンズメイトで、なぜかボタンの代わりに一か所だけ謎のフックが付いているシャツを見つけて「これ、オシャレじゃん」と思い、お小遣いで買いました。当時の私にとっては「謎フック」=「洗練」だったのです。
Tシャツはグレイトフルデッドベアの顔がワンポイントで入った白T。そこに、安物の十字架ネックレスを合わせることで「個性爆発」を目指していました。今なら完全に怪しい宗教の信者に見えなくもないですが、当時は本気でかっこいいと思っていたのです。
高校時代:B系への道
私の高校は渋谷の近くにあったため、放課後に原宿まで歩いて服を見に行くこともしばしば。
当時のユニクロは今ほどブランド感もなく、「ちょっとダサい」みたいな風潮もあり、私は見向きもしませんでした。
代わりに好んでいたのは、B系男子御用達のショップ。ダボダボでビビッドカラー、ペンキをぶちまけたようなロンTに惹かれていたのです。あの頃の私は、服のサイズ感も色合いも「控えめにする」という概念を知らなかったようです。
そして、高嶺の花だったフレッドペリーのジャージ。頑張って手に入れました。インナーはキレイ目、アウターはスポーティ、というのが流行っていたと記憶しています。ちなみにこのジャージ、後に20年近く実家の母が愛用することになります。よほど着やすかったのでしょう。
また一時期、なぜか“綺麗目シャツに綺麗目ジャケット”という、ほぼフォーマルな恰好にハマり、卒業旅行にそのスタイルで登場。周囲から「なんか大人っぽいね」と言われましたが、あれはどう考えても皮肉でした。完全に浮いてましたから。
大学生、古着とセレクトショップの狭間で
大学時代、ついに毎日が私服という試練にさらされることになります。
1~2年生の頃は神奈川のキャンパスだったので、町田の古着屋をめぐっては、掘り出し物(という名のクセ強めの服)を漁っていました。
3~4年生になると渋谷のキャンパスになり、雰囲気が一転。セレクトショップに足を踏み入れ、「メンズノンノ」を参考に服選びをするようになります。
特に気に入っていたのがShipsとジャーナルスタンダード。今思えば、両者の方向性は全然違うのですが、なぜか両方とも「これは俺のスタイルだ」と信じて疑いませんでした。今なら「どっちだよ」とツッコミたくなります。
社会人、そしてスーツに命をかけ始める
社会人になってからも、私服熱は一時的に続いていました。というか、Shipsとジャーナルスタンダードをひたすらローテーションしていた記憶があります。
ただ、あるときから急速にスーツへのこだわりが強くなっていきました。スーツは戦闘服。勝負服。そう思い始めたのです。
ちなみに、現在勤務している税務署では黒スーツがスタンダードです。しかし私は黒スーツを一着も持っておらず、ネイビーやチャコールグレーのスーツばかり着ています。というか、黒以外の方が本来スタンダードなのでは?と密かに思っています。誰にも言っていませんが。
そして今:ユニクロと向き合う日々
ここ数年、私服はユニクロとGUが中心になっています。というのも、2015年ごろからユニクロのブランド価値が一気に上がり、「とりあえずユニクロに合わせておけば、そんなに外さない」という安心感があるからです。
トレンドも適度に取り入れてくれていますし、何より、服を選ぶのにかける時間とエネルギーを削減できるのが大きい。今は「ミニマルで機能的な服」を選ぶようにしています。あと、ユニクロの服が似合う体型を維持しておけば、少なくとも人様に不快感は与えずに済む気がしています。たぶん。
独立後の服装問題
さて、今年の夏には税務署を退職し、独立する予定です。そうなるとまた、私服の課題に向き合う必要があります。
クライアントと直接会うことがなければ、スーツを着る意味はあまりありません。しかし、パジャマのままで仕事するのも何だか気が引ける。切り替えの意味でも、やはり「部屋着ではないけれど、かしこまりすぎない服」を選びたいのです。
…となると、やっぱりユニクロに戻ってくるんですよね。便利って、罪。
以上、私服というテーマを通して、私の過去と現在が垣間見えるお話でした。私のパーソナルな部分が、ほんの少しでも伝わればうれしいです。
このあとも、黒歴史を供養するような記事が続くかもしれません。どうぞお付き合いください。

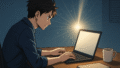

コメント