ひとり税理士としての独立準備を進める中で、ホームページ作りにも着手しはじめました。これまで国家公務員として働いてきた私にとって、「事務所のホームページを自分で作る」なんてことは、正直ちょっとしたカルチャーショックでもあります。
ただ、その一歩を踏み出してみると、案外楽しく、そして創造的な作業であることに気づきました。役所仕事ではなかなか味わえなかったこの“自分で形を作っていく感じ”、ちょっとクセになりそうです。
独立の先輩方からの学び
独立を考えるようになってから、ひとり税理士としてすでに活動されている方々の情報発信にたくさん触れてきました。kindle unlimitedなどで公開されている開業初期の体験談や、X(旧Twitter)・note・ブログでの知見共有は、どれも実践的で非常に参考になります。
驚いたのは、こうした貴重なノウハウを惜しげもなくオープンにしてくれる方が本当に多いということです。もちろん中には高額な情報商材的なものもあるのかもしれませんが、私のように手探りで準備している者にとっては、「まずは無料で読める範囲から」で十分な気づきをもらえる世界です。
このオープンな情報共有の雰囲気、なんだかプログラマー界隈でよく耳にする「オープンソース文化」と似ているなと感じます。実際にその分野のことはあまり詳しくないのですが、ネット上で無償で学べて、学んだ人がまた何かを還元する。その循環が今の士業界にもあるように思います。
ブログとホームページは車の両輪
ブログを書き始めたのも、「独立前の練習」のつもりでした。実際、自分の考えを言語化し、伝えるという作業は、税理士として開業後に必ず必要になるスキルだと感じています。
ただ、書き続けているうちに、これは練習ではなく「自分の軸」そのものになりつつあると気づきました。ホームページも同じです。表面的な情報だけでなく、「誰が、どんな思いで、何をしているのか」を伝える場として、きっと私の事務所にとって欠かせない存在になるでしょう。
ひとり税理士の先輩方もほぼ例外なく、ブログとホームページをセットで運用されています。その理由が、少しずつ自分の中でも腑に落ちてきました。
無償の情報がありがたい
士業向けのホームページ制作ノウハウについても、検索すればたくさんの情報が出てきます。なかには業者に依頼する前提の記事もありますが、「自作でも十分」という声も少なくありません。WordPressを使った構築方法、文章の書き方、配色のポイントなど、手取り足取り教えてくれるような内容のサイトもあります。
そして何より、こうしたノウハウの多くが“無料”で公開されていることに感動すら覚えます。これは本当にありがたいです。私も今後、ホームページ作りを通じて得た気づきは、どこかで何かしら還元していけたらと思っています。
公務員生活にはなかった“創る”という楽しさ
税務署での仕事は、基本的には「決められた制度をどう運用するか」という世界でした。それはそれで奥が深く、実務的な面白さもあるのですが、自由に「表現する」という方向性とは少し距離があります。
ホームページ作りはその真逆です。どんな色にするか、どんな言葉を載せるか、どのページ構成にするか――すべてが自分次第。これが想像以上に面白いのです。今後はロゴや名刺のデザインなどにも手を広げていくつもりで、きっとそこでも同じような楽しさがあるのだろうと思っています。
私が参考にしている二つのサイト
ホームページ作りにあたって、実は私が大いに参考にしているのが、まったくジャンルの異なる二つのウェブサイトです。
一つ目は「極限攻略データベース」というゲーム攻略サイトです(こちら)。学生時代から『ドラクエ』シリーズの攻略で何度もお世話になってきたサイトですが、今あらためて見るとその構造が非常に秀逸です。
情報の分類が直感的で、どこに何があるのかすぐにわかる。ユーザーの「知りたい」に対して、迷わせることなく答えを提示してくれる構成になっています。この「迷わせない設計」は、税理士事務所のホームページにも通じる部分があると感じています。
もう一つは、実業家マコなり社長が代表を務める株式会社Surpriseの公式サイトです(こちら)。シンプルな白背景に大きめのフォント、余白を生かしたメッセージ重視の構成。装飾を削ぎ落としたそのデザインには、ある種の美しさすら感じます。
両者は全く違う方向性のサイトですが、それぞれに大きな学びがあります。良いなと思った部分はまず模倣してみる。そこから、少しずつ自分らしさを加えていく。これはホームページに限らず、仕事でも生き方でも共通する大事な姿勢だと思っています。
今後に向けて
ホームページ制作も、ブログの執筆も、独立準備の一環ではありますが、それぞれが自分を知ってもらうための重要なツールだと感じています。そして、それを通じて自分自身の考えや立ち位置が見えてくるというのは、副次的なようで本質的な効用かもしれません。
まだまだ手探り状態ではありますが、焦らず少しずつ、“自分らしい”事務所のかたちを作っていきたいと思います。

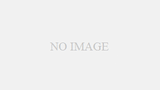
コメント