税務署の審理担当として電話を受けていると、よく尋ねられることがあります。
「この処理って、これでいいんですよね?間違いないですよね?」
念押しのように確認されたかと思えば、「部署とお名前、伺ってもいいですか?」と続くのが、いわゆるセット技です。
たしかに、ある程度の規模の会社であれば、担当部署の責任として「〇月〇日に△△税務署■■氏に確認済」という記録を残しておくことには意味があると思います。何かあったときの“証拠”として扱えることを期待しての行動なのでしょう。
ただ、その証拠が、本当に保証になるかというと、話はまったく別です。
税務署の職員は保証しない
税務署に勤務していると、つくづく思うのですが、私たち税務職員は「保証を与える存在」ではありません。申告納税制度という制度のもと、納税者が自ら判断し、自ら責任を持って課税標準及び税額を確定する。これが日本の税制の大原則です。
たとえば、税務調査の現場で「非違事項なし」となった場合。これは「正しい申告でしたね、お墨付きです!」という意味ではありません。あくまで、「更正・決定すべきとは認められなかった」というだけ。ですので、税務署から出る通知書にも、きちんとそのように書かれています。
このあたり、「是認=正しかった」のように受け取る方もいらっしゃるのですが、是認とは「今この段階ではそれ以上の指摘をしないという判断」に過ぎません。将来にわたってその申告内容を保証するわけではないのです。
届出と申請は似て非なるもの
「届出を出したけど、税務署から何も反応がない。これは認められたということでしょうか?」
これもまた、よくいただくお問い合わせの一つです。特に、事前確定届出給与に関する届出の場面で多く見られます。
しかしながら、「届出」はあくまで届出であり、「申請」ではありません。法律上の効果の発生タイミングが異なりますし、税務署側の承認という行為を伴わない場合がほとんどです。
一方、「承認申請」については、申請から〇か月以内に通知がなければ“みなし承認”とする、といったことが法律上謳われているものもあります。こちらは、ある意味「保証」に近い性質を持つわけです。
その違いを理解せず、全ての届け出や質問に対して「保証」的な回答を求められると、こちらとしてもどうにも対応のしようがありません。
保証を求めるマインドの落とし穴
少し脱線しましたが、私が言いたいのは、「保証を求めるマインド」は、税務署職員としても、そして今後税理士として働く身としても、予後が悪いということです。
納税者からの問い合わせだけでなく、税理士やその事務所の職員からも、時に強めの口調でこう尋ねられることがあります。
「これで大丈夫ってことですよね?もし間違ってたら、税務署の責任ですよ?」
いやいや、ちょっと待ってください。それを判断するのがあなたのお仕事ではないのですか?と喉元まで出かかった言葉を飲み込む日々です。特にOB税理士、アンタらのことだよ
もちろん、納税者の立場に立って誠実に対応することが公務員の務めです。しかし、それと「判断を肩代わりする」ことは違います。責任を持って判断するのは、あくまでご自身。そこに“保証”を外部に求めるマインドが入り込んでしまうと、思考がストップします。
ガチャ切りの電話が教えてくれたこと
最近では、税理士資格のない会計事務所の職員から、カジュアルに質問を受けることもあります。所轄署の法人であるかを確認するため、法人名を尋ねると、突然ガチャ切りされる——そんなことも。
「名前を名乗っていないからセーフ」と思っているのかもしれませんが、電話の向こうでそうした不義理が繰り返されていると、正直、組織として対応のレベルも見られてしまいます。たとえ今日うまく逃げられても、長い目で見れば損をするのはその事務所自身ではないでしょうか。
自分の頭で考え、行動するということ
税理士として独立を控える今、改めて思うのです。保証を求めるマインドで日々過ごしていると、自分自身の成長の機会を失ってしまう、と。
私自身も、何度も「これはこうでいいのか?」と誰かに聞きたくなる場面に直面してきました。でも、そのたびに調べ、考え、納得いくまで試行錯誤することで、ようやく「これは自分の判断だ」と胸を張れるようになったのだと思います。
たしかに、誰かに保証してもらえると安心はします。でも、安心が得られたとしても、それで良い仕事ができるかというと、それはまた別の話です。むしろ、安心を得ようとするあまりに、誤った判断をそのまま進めてしまうリスクすらあるのです。
さいごに
この記事は、半分は自戒の意味も込めて書いています。保証を求めたくなる気持ちは、私にもあります。ただ、保証の先にあるのは「責任転嫁」であって、「納得のある判断」ではないと思うのです。
税務に限らず、人生のあらゆる局面で、自分の頭で考えることを怠らない。その姿勢があって初めて、プロとしての信頼や、自分自身の納得のある選択が生まれてくるのではないでしょうか。
「この道を行けばどうなるものか——踏み出せばその一足が道となる」。
保証なんてなくたって、ちゃんと道はできます。

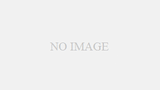
コメント