国税時代は「わからない」と言いづらかった
「わからないことはわからない」――たったこれだけの言葉ですが、現職時代は口にするのが難しかったです。
税務署や国税局で仕事をしていた頃、上司から「これどうなってる?」と聞かれると、即答できるのが当たり前の雰囲気がありました。もちろん、間違った答えを出すのは論外です。ただ、質問される内容の大半は、日々の業務をきちんとこなしていれば答えられるようなものだったからです。
特に若手の頃は「わからない」と言うこと自体が、自分の無能さを証明してしまうような気がしていました。たとえば、調査から帰ってきて統括に復命する際に、きちんと確認していない事項について統括から問われたとき。どこか歯切れの悪い答えを返していたことを思い出します。今振り返ると、潔く「そこは確認していません。なので先方に確認してきます」と言ったほうが誠実でしたし、余計な憶測を排除できたはずです。
さらに思い出すのは、会議でのやり取りです。幹部より、事案が飛ぶほどではないタイプの素朴な質問があることがあります。本当は即答できるほど詰めていなくても、何か言わなければ場が止まってしまう。その空気に負けて、やや具体性に欠ける表現で切り抜けたことが何度もありました。最初から「わかりません、確認します。」と言っておけば良かったと思います。
無職になって気づいた変化
独立に向けて無職となった今は、そのあたりのプレッシャーから解放されました。最近は質問箱に寄せられた匿名の質問に答えていますが、これがまた意外とわからないことが多いのです。税務や国税の内部事情について聞かれることもありますが、必ずしも一刀両断できるものばかりではありません。「それは一概に何とも言えませんが、こういう考え方もあります」「この部署は勤務経験が無いので憶測になりますが」といった留保付きの回答が増えます。時には塩対応気味に見えるかもしれませんが、正直なところをごまかさず伝えたいと思っています。
組織文化が生んだ「即答プレッシャー」
国税時代を思い返すと、「わからない」を避けていたのは組織文化の影響もありました。上司にとって「わからない」ままでは決裁が通らない。即答が組織を前に進める潤滑油でもあったのです。
もちろん、即答力は調査現場でも役立つスキルですし、判断のスピードは納税者対応にも必要です。ただ、その裏で「わからない」と言えない空気が、自分の首を絞めていたのも事実です。調査先でも、その業界特有の商流や慣習について「そんなことも知らないのか」と法人の代表者に言われることもありました。準備調査を尽くしてもわからないことは当然あります。そのとき、わからないことをきちんと認めて教えてもらい、その場で解決していれば良かったと思います。後日になって「ところで、あれってこういうことですか?」と確認しても、「今さら何を」と思われてしまいます。
「わからない」を言える自由
いま私が「わからない」と言えるのは、立場の変化が大きいと思います。無職というと聞こえは悪いかもしれませんが、税理士登録を控えた今は、誰に忖度するでもなく自分のペースで知識を吸収できます。質問箱も以前に比べれば気楽です。
ここで少し余談ですが、「わからない」を素直に言えた人物として織田信長の名前が浮かびます。宣教師ルイス・フロイスとの対話で、信長は「雷はなぜ光るのか」「なぜ音を伴うのか」と素朴な疑問を投げかけ、説明を受けて納得したと記録されています。一方で、キリスト教の神という存在については「人が目に見えぬものを信じるのは理解できぬ」と首をかしげたとも伝えられています。つまり、信長は「知らないことは知らない」と受け入れ、納得できることは学び、納得できないことは納得できないままにしておく柔軟さを持っていたのです。時代も立場も違えど、学ぶ姿勢は大いに見習うべきだと思います。
一方で、現代に目を向けると、YouTubeでは「節税!」「これをやれば経費に!」と断定口調で語る人たちをよく見かけます。インプレッションを稼ぐにはセンセーショナルな発言が必要なのかもしれませんが、税理士の実務はそんなに単純ではありません。◯◯なら必ず◯◯できる、と断言できることは少なく、むしろ個別具体的な事情によって結論が変わると説明するのが正直なところです。国税時代、数え切れないほどの事案を検討しましたが、同じ条文でも、事実関係が少し違うだけで結論は変わります。だからこそ、専門家が「断定できません」と言うのは逃げではなく誠実さなのだと思います。
税理士としてのこれから
これから税理士として働くにあたり、私は「わからない」と言える姿勢を大切にしたいです。クライアントに質問されたとき、即答できなければ「確認して後日回答します」と言う。調べれば答えられることは必ず調べ、どうしても断定できないことはその旨を説明する。シンプルですが、これこそが信頼につながるのではないかと感じています。
「わからない」をなかなか言えずにいた国税時代も、今思えば大事な経験でした。当時の葛藤があったからこそ、いま「わからない」を素直に口にできる心境にたどり着けたのだと思います。もしこの記事を読んでいる方の中に「わからないと言えない」と悩んでいる方がいたら、わからないことを「わからない」と言える人間が強いんだということをお伝えしておきます。

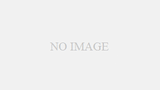
コメント