最近の1年目職員を見ていて、ちょっと思うことがあります。いや、だいぶあります。
いえ、別に愚痴りたいわけではないんです。ただ、国税の職場における「1年目の扱い方」が、あまりに優しすぎやしないか、ということをつい考えてしまうのです。
もちろん、誰にでも社会人1年目はありますし、誰だって最初は分からないことだらけです。それは私だってそうでした。ですが、近年はどうもその「分からないことだらけ」な状態に、周りが過剰に手を差し伸べている気がするのです。
大卒採用で入庁してくる若手たちは、いきなり課税部門に配属され、早々に税務調査に出て現場デビューを果たします。これは一見すると実践的で良さそうに聞こえます。が、問題はその後です。
彼・彼女らの周りには、多くの場合、再任用の職員等の若手指導育成担当がいます。これは制度上、非常にありがたい仕組みではあるのですが……なんというか、指導というよりも「お世話」になっている場面が目立つのです。
再任用の職員が「若い子と仲良くやるのが大事だからね」と言うのはまだ理解できます。ただ、見ていると「嫌われたくない」一心で接しているように見えることが少なくありません。中でも、容姿の整った女性職員に対する男性の指導担当の様子は、もはや公私の境界が甘くなっているように感じることもあります。
職場って、そもそもそういう評価軸で成り立つ場所ではないと思うのです。
さらに言えば、担当統括官もどこか及び腰です。「指導の仕方を間違えて、メンタル病まれたら…」とか「パワハラと言われたら…」とか、そんなことばかり気にしているように見えます。いや、もちろん現代のコンプライアンス意識は大切です。でもその一方で、「育てる」という視点がどこか薄れているのも事実です。
私の若い頃は、とりあえずやってみろ、考えて動け、という文化でした。考えて失敗して、それでも動いたことに対して指導がありました。ある意味、答えのない中で自分の思考と経験を積み重ねるしかなかった。
でもそれが、結果として自分の頭で考える力や、自信、そして責任感につながっていたのだと思います。
今の若手職員は、最初から全部教えられ、サンプルの掲載場所を教えられ、管理職としては、部下のミスを未然に防ぐための説明責任は形式的に果たしています。失敗させたくない気持ちはわかります。けれど、それって育てているのではなく、守っているだけじゃないですか。
その結果、「自分で調べて判断する」という基本動作ができなくなっているように思えます。
「それってどこに書いてありますか?」
「この処理、どこまでやればOKですか?」
「この資料は、何分割してもっていけばよいですか?」
……とにかく一から十まで、マニュアルか誰かの口からの「正解」が出るのを待っている。その間、机の前では手が止まっている。
そして、その手が止まったままの状態を見て、管理職が気づいてしまい、結局その案件を巻き取って処理する、という悪循環。
「せめてやりかけでもいいから、着手した証拠だけでも残してくれ…」と思ってしまいます。
こんな風に、社会人生活1~3年目を蜂蜜漬けで過ごしてしまうと、その後の予後がどうにも悪そうでなりません。糖度たっぷりのぬるま湯にどっぷり浸かって、いざ本当に責任のある仕事を任されたときに、うまく動けない。自分で考える力が育たないまま年次だけ重ねてしまう。
最悪なパターンは、「私たちの頃にはちゃんとした指導がなかった」と逆ギレ……もとい、被害者意識を持ち始めることです。いやいや、それって育ててもらう姿勢すら持っていなかったんじゃないの、という話です。
とはいえ、こういう話をしだすと「昔はよかった」的な、いわゆる“昔話おじさん”のように思われてしまうのが今の時代の難しいところです。
職場を去ろうとしている身で「私の若い頃は~」と語りすぎるのもダサいのでこれくらいにしておきます。
ただ、ほんの少しでもいいから、「自分で考えて動く」という原点に立ち返る時間を、今の若手にも持ってもらいたいなと思うのです。失敗してもいいから、とにかくやってみる。その中で見えてくるものがある。それが社会人1年目の本当の学びだと思うのです。
どうか、ほどよく発酵しながら、甘すぎない社会人になっていってほしいものです。
蜂蜜漬けにされたままでは、味はいいけど、消化に悪いですからね。

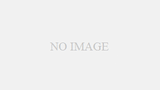
コメント