独立を前に、これからの資産形成や税制をどう組み合わせていくかをあらためて考える機会が増えました。その中で特に悩ましいのが、iDeCo(個人型確定拠出年金)の出口戦略です。
iDeCoは節税効果が大きいと言われますが、受け取り時に課税関係が発生します。拠出時に所得控除を受けた分、最後に帳尻合わせが待っているわけです。ここを理解しないと、思った以上に税負担が生じる可能性があります。私自身もシミュレーションを繰り返して整理がついたので、今回はその内容を共有します。前提は、一時金で受け取る場合のケースです。
退職金とiDeCoを同時に受け取るとどうなるか
ここで重要なのが「退職所得控除の復活ルール」です。
- サラリーマン退職金とiDeCoを同じ年に受け取ってしまうと、控除は1回分しか使えない。
- 以前は「5年ルール」といって、退職金を受け取ってから5年以上経過すれば控除を別に使えるとされていました。
- しかし、令和7年税制改正で「10年ルール」へと厳格化され、10年以上空けないと控除が復活しないことになりました。
さらに注意すべきは、退職金が先・iDeCoが後の順番の場合です。
この場合には「19年ルール」が適用され、退職金から19年以内にiDeCoを一時金で受け取ると、控除は合算扱いになってしまうのです。
つまり、
- 退職金 → iDeCoの順に受け取る場合、19年以内は控除が分けて使えない
- 退職金とiDeCoを「別の年」にずらすだけでは不十分で、年数の経過要件を満たさなければならない
という厳しい規定です。
私の場合、2025年に国税職員を退職し退職金を受け取りました。iDeCoを受け取るのは60歳以降(2046年以降)なので、19年以上の間隔が自然に確保できる形になります。したがって、私自身は控除を分けて使える見込みですが、会社員や公務員の方が「退職金と同時にiDeCoも60歳で受給」とすると控除が一回分しか使えないという点は注意が必要です。
シミュレーションしてみた結果(前提条件)
ここからは、実際に私の数字を置いたシミュレーションです。
前提条件は次の通りです。
- 既存資産:245万円(拠出元本125万円+含み益120万円)
- 拠出額:2026年以降、制度上限の月7.5万円(年90万円)で拠出したケースを想定
- 運用利回り:年6%(複利)
- 受け取り:一時金(退職所得扱い)
60歳で受け取る場合
- 資産額:約4,600万円
- 控除枠:1,430万円(29年分)
- 超過分:約3,170万円 → 退職所得の1/2課税対象
- 非課税で収めるための拠出限度:年間約14.1万円(月額約1.2万円)
65歳で受け取る場合
- 資産額:約6,200万円
- 控除枠:1,780万円(34年分)
- 超過分:約4,420万円 → 退職所得の1/2課税対象
- 非課税で収めるための拠出限度:年間約11.4万円(月額約9,500円)
👉 このように、フル拠出してしまうと控除枠を大幅に超えて課税されることがわかります。
手数料体系と簿価の扱い
iDeCoは拠出をしてもしなくても、最低限の管理手数料がかかります。
- 国民年金基金連合会:月105円
- 信託銀行:月66円
- SBI証券(運営管理機関):月0円
合計すると、月171円は必ず発生します。
つまり「拠出ゼロ」でも171円は払い続ける仕組みです。
また、簿価(平均取得単価)の扱いについても整理しておきます。公務員時代の拠出金と、今後個人事業主として拠出するお金が同じ投資信託に入れば、それぞれの購入価格は合算されて平均化されます。別々に簿価が残るわけではなく、時間の経過とともに一つの投資単価として収斂していくイメージです。
最低拠出にした理由
では、なぜ私は月額5,000円に決めたのか。理由は大きく2つあります。
第一に、新NISAの方が流動性も高く、使い勝手も良いと考えているからです。限られた資金を効率的に使うには、まずはNISA枠を優先的に埋める方が合理的だと判断しました。
第二に、iDeCoはすでに「手を上げている」状態なので、拠出しなくても毎月171円の手数料が差し引かれます。それなら最低限の5,000円だけでも入れておく方が納得感があります。控除枠ギリギリに合わせて月1万円前後にすることも可能でしたが、経済成長や運用成績が想定以上に上振れすると結局は控除枠を超えて課税される可能性が残ります。だったら割り切って最低拠出額にとどめておく方が、シンプルで安心だと考えました。
まとめ
iDeCoは確かに節税メリットのある制度ですが、出口戦略を誤ると「課税されてしまうからやらなければよかった」と感じる可能性もあります。さらに令和7年改正で「退職所得控除の復活年数」が5年から10年に延びた上に、従来からの「19年ルール」も健在です。
私の場合は退職金をすでに受け取り、iDeCoは19年以上空けて受け取る予定なので控除を分けて使えますが、多くの会社員や公務員にとっては「退職金と同時受給」や「10年・19年以内の受給」に注意しないと、控除が合算されて課税されるリスクがあります。
最終的に私は、月額5,000円の最低拠出にとどめるという判断をしました。これは「税負担を最小化しつつ、新NISAで攻める」というシンプルな戦略です。
読者の方にとっても、出口戦略を意識して制度を使うことの重要性を感じてもらえればと思います。

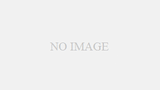
コメント