珍しく税金に関する記事を書きます。相続財産法人についてです。
税務署で審理担当をしていた頃、税理士の方からよく聞かれたのが「相続財産法人って法人税の申告、必要なんでしょうか?」という質問です。
たしかに、頻繁にあるケースではないものの、相続人がいないまま遺産が宙ぶらりんになったとき、突如として“相続財産法人”という存在が浮上してきます。そしてその瞬間から、税理士の方が最初に頭を悩ませるのが、法人税の申告義務の有無です。
今回は、あらためてこのテーマを整理しておこうと思います。専門寄りの内容ではありますが、税理士・士業の方の参考になれば幸いです。
相続財産法人とは?民法上の規定と法人格
そもそも相続財産法人とは、民法第951条に定められている制度です。
相続人のあることが明らかでない場合、または相続放棄などにより相続人がいない状態になった場合、その遺産は「相続財産法人」として扱われます。これは、登記などの法人設立手続きを経るものではなく、相続開始の時点で当然に法人格を持つという、非常に特殊な仕組みです。
相続財産管理人が裁判所によって選任され、その人が法人の代表のような立場で清算や管理を行っていきます。最終的には債権者への弁済、特別縁故者への財産分与、そして残余財産があれば国庫へ帰属する、という流れです。
法人税法上の位置づけは「普通法人」
次に法人税法上の位置づけですが、相続財産法人は「普通法人」に該当します。
法人税法第2条では「内国法人」が定義されており、そのうち公益法人等や協同組合等以外のものを「普通法人」としています。相続財産法人は、これらの非課税法人のいずれにも該当せず、また設立登記を経ていないとはいえ、法人格を有していることに変わりはありません。
そのため、税法上は普通法人として取り扱われ、形式的には法人税の申告義務があるというのが法令上の建て付けです。
所得がなければ申告不要?
問題はここからです。
「申告義務はある」と言っても、実際に相続財産法人が何ら活動しておらず、所得も一切ない場合、本当に申告しなければいけないのか?という疑問が残ります。
私の実務経験でも、税理士の方からは「相続財産法人を設立する届出や、申告書を出すつもりはないですが、それで問題ないでしょうか?」という“お断り”のような照会が何度もありました。
結論からいえば、所得が発生していないなら、申告書を提出しなくても実害がないケースが多いです。少なくとも税務署側から積極的に「申告書を出してください」と連絡することは、私の知る限りではほとんどありませんでした。
これは相続財産法人の特殊性、つまり最終的に残った財産が国庫に帰属するという仕組みに由来します。要するに、法人税を課しても結局は国のお金になるわけで、課税の意義が希薄になりがちなのです。
ただし課税されうるケースも
だからといって、すべてのケースで申告不要になるわけではありません。
例えば、相続財産法人が不動産を貸し付けて賃料収入を得ていたり、上場株式を売却して利益が発生していたりする場合、その所得に対しては当然に法人税が課されます。つまり、「相続財産法人であっても課税されることはある」のです。
また、特別縁故者に対して財産分与が行われる場合、不動産を売却して現金化してから分与することもあります。その過程で譲渡益が発生しているとすれば、これも法人税の課税対象になります。
このように、実質的な所得が発生しているかどうかが、申告義務の有無を左右する重要なポイントです。
設立届や申告案内はどうなっているのか
法人が新たに設立された場合、税務署には「法人設立届出書」を提出するのが通例です。ただし、相続財産法人は登記や届出によって成立するものではないため、形式的な設立届出が行われないまま進行するケースも多いです。
税務署としても、商業登記で把握できる法人ではないため、そもそも相続財産法人の発生自体を知らないということもあり得ます。実際、私が受けた照会についても、そうしたケースは珍しくありませんでした。
したがって、法人税の申告案内が届かないまま、管理人の判断で無申告のまま清算されてしまうこともあります。
「双方にとってウィンウィン」なのか?
このような実務の流れから、「申告しないことが双方にとってウィンウィンなのでは?」という感覚を持たれる方もいらっしゃると思います。実際、私もそう感じることがありました。
何もしていない法人に対して申告書の提出を求めることもなく、税理士側も申告書の作成という手間を省ける。お互いにとって悪い話ではありません。
ただし、この感覚には注意が必要です。たとえ今は申告不要と考えていても、後に譲渡や収益の発生があったことが判明すれば、結果として無申告加算税などのリスクが出てくることもあり得ます。
ですので、「今回のケースでは本当に申告が不要なのか?」という点は、状況をよく確認してから判断する必要があります。
最後に
相続財産法人に関する法人税の申告義務について、私自身の審理経験をもとに整理してみました。
条文や法令の建て付けを重視すれば「申告義務あり」という結論になりますが、現場の実務では「所得がなければ申告せず」という対応も少なくありません。
税理士の方におかれては、形式的な義務と実質的な経済活動の有無を照らし合わせながら、個別に判断していくのが現実的な対応かと思います。
少しでも参考になれば幸いです。
参考文献
- 民法第951条
- 法人税法第2条
- 国税通則法第5条
- 日本税務研究センター「相続財産法人の納税義務」相談事例
- 税理士法人トゥモローズ「相続人不存在の場合の相続手続きガイド」
- ネクスパート法律事務所コラム「相続財産法人とは」
- 税務通信・週刊税務通信各号(相続財産法人関連の実務解説)
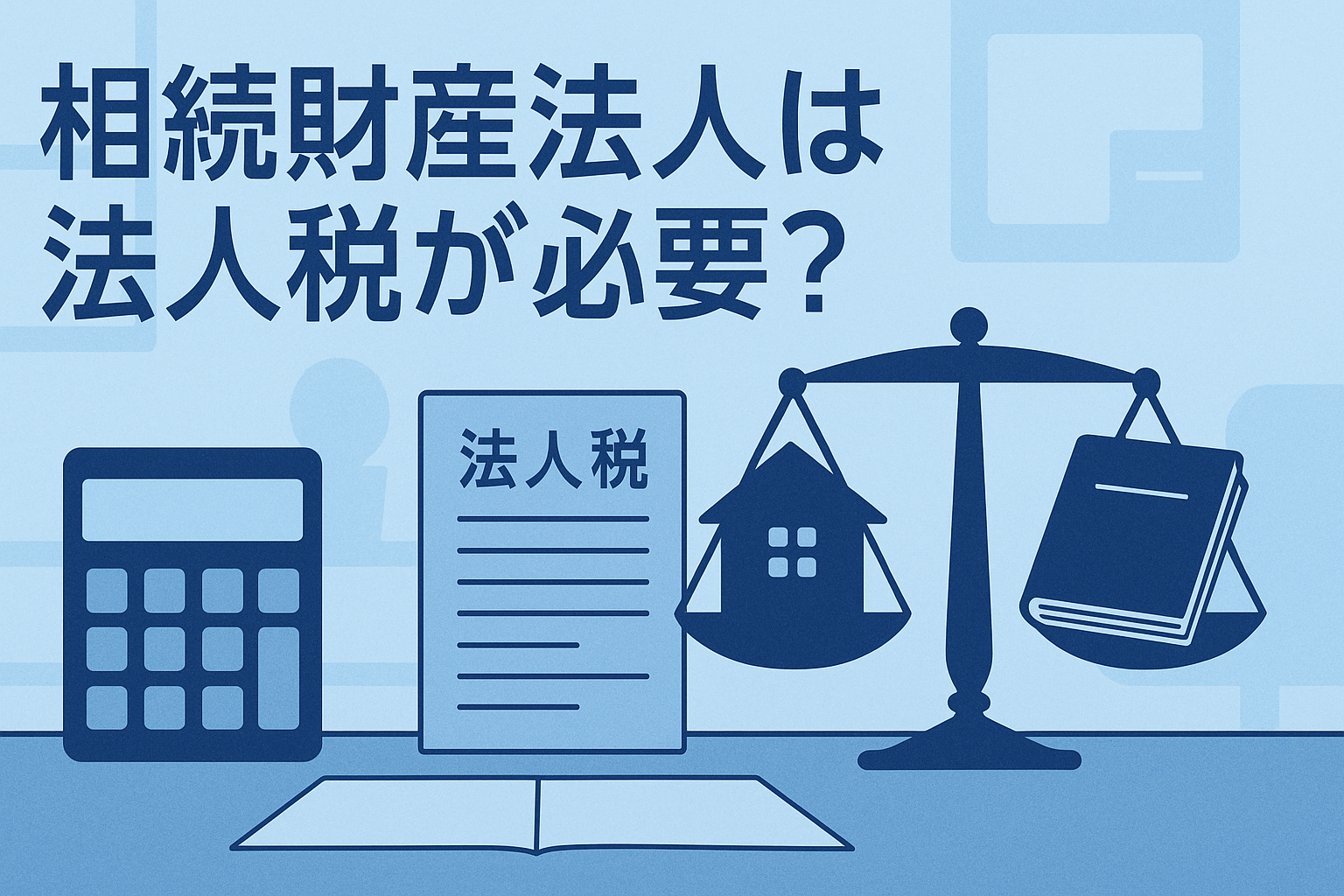


コメント