開業を考えるとき、多くの人がまず気にするのは「法人化したほうが得かどうか」という税金の話です。
たしかに、所得が一定以上になると法人の方が節税になる場面もありますし、経費の範囲も広く見えることがあります。
けれども、冷静に考えてみると、税制の損得だけで経営形態を決めるのは少し危ういように思います。
なぜなら、「個人か法人か」というのは、そもそも税金以前に「責任の取り方」の問題だからです。
その本質を意識せずにスタートしてしまうと、いざトラブルが起きたときに初めて“法人であることの意味”に気づくことになります。
無限責任と有限責任という分かれ道
個人事業主は、法律上「事業=自分」です。
つまり、事業で負った借金や債務はそのまま自分個人の借金になります。たとえば、仕入代金の支払いが滞ったり、取引先とのトラブルで損害賠償を請求された場合、個人の貯金や自宅までもが責任の範囲に入ってきます。これが「無限責任」です。
一方、株式会社や合同会社などの法人は、法律上「自分とは別の人格」を持っています。
社長や社員(出資者)は「出資した金額の範囲でしか責任を負わない」。これが「有限責任」です。
会社が1,000万円の借金を抱えて倒産しても、社長個人がその1,000万円を背負うわけではありません。会社と個人の財布は分かれており、原則として会社の資産だけで清算します。
もちろん、現実には金融機関の借入などで代表者が連帯保証人になるケースが多く、完全に切り離されるわけではありません。けれども、「責任の基本構造が違う」という点は非常に大きな意味を持ちます。
法人をつくるということは、「リスクを自分の外に出す」行為でもあるのです。
税金よりも先に考えたい「信用」と「資金」の話
もう一つ、個人と法人の違いを感じやすいのは「信用」と「資金調達」です。
個人事業主のままでも事業は十分に成り立ちますが、銀行や取引先の見る目はやはり少し違います。
たとえば法人名義で契約書を交わすと、それだけで相手に「一定の事業体として整っている」という印象を与えます。契約書、請求書、印鑑証明、登記簿謄本——そうした書類が整うだけで、取引の安心感が生まれるのです。
資金調達の面でも差はあります。
個人の場合、事業の借入はあくまで「個人名義の融資」になります。銀行は個人の信用情報や所得をもとに審査しますが、法人であれば会社としての財務や売上見通しを評価します。
法人の方が借入の枠を広げやすい傾向がありますし、出資を受けて資本を増やすことも可能です。個人事業では「自分のお金だけ」でしか動けないのに対し、法人は「他人のお金を使って拡大できる」構造を持っています。
もっとも、小規模な事業なら自己資金で十分に回りますし、むやみに借入を増やす必要はありません。
ただ、「自分の事業をどこまで広げたいか」という中長期の視点を持ったとき、法人の形態が自然と選択肢に入ってくるのだと思います。
二元論では一概に語れない
個人事業はとてもシンプルです。始めるのも終わるのも簡単で、税務の手間も比較的少なく済みます。
一方で、法人は登記や会計処理など一定の手続きを要し、維持コストもかかります。けれども、その分だけ法的な守りが強く、取引先からの信用力も高まります。
また、事業を続けていると、ある年に思いがけず数千万円といった大きな利益(いわゆる「爆益」)が出ることがあります。
このとき、法人という「箱」を持っていなければ、累進課税の影響で所得税や社会保険料によって利益の半分以上が失われてしまう場合があります。日本の税制は、高所得者に対して非常に厳しい仕組みになっているためです。法人を設けることで、この所得の偏りを平準化し、リスクをやわらげることができます。
もっとも、個人と法人の違いを「攻めか守りか」という単純な二元論で語るのは不十分です。
実際には、事業モデルの性質によっても法人化の価値は大きく変わるかと思います。
たとえば、有形物を扱うビジネス――不動産、車両、設備、在庫など――を販売する場合は、融資を受けて事業を拡大する「金融レバレッジ」を効かせることができます。
このとき、法人であれば資金調達の自由度が高まり、内部留保を積み上げてより大きな投資に挑戦しやすくなります。万が一、失敗したとしても、有限責任という盾が個人資産を守ってくれる。まさに「挑戦できる構造」が整っているのです。
一方で、デザイン、コンサルティング、教育、執筆といった無形物を扱うビジネスでは、初期投資が少なく、金融レバレッジをかける余地は限定的です。その分、法人化による“守りの効果”は相対的に小さくなります。もっとも、法人としての信用力や、税負担の分散効果といった側面では、依然として有用です。
結局のところ、法人化は「攻めか守りか」ではなく、どんな資産を軸に、どんな成長を描くかという戦略の問題だと理解しています。
生活と事業が密接に結びついている段階では個人事業で十分ですが、資金を動かし、他者と関係しながら拡大を目指す段階では、法人という器が現実的な選択肢になってきます。
法人化は節税のための小手先の手段ではなく、リスク・信用・資金の流れをデザインするための制度的なツールです。
自分の事業の性質を見極めたうえで、どんな「器」で挑戦するのが最適なのかを考えることが肝要だと思っています。
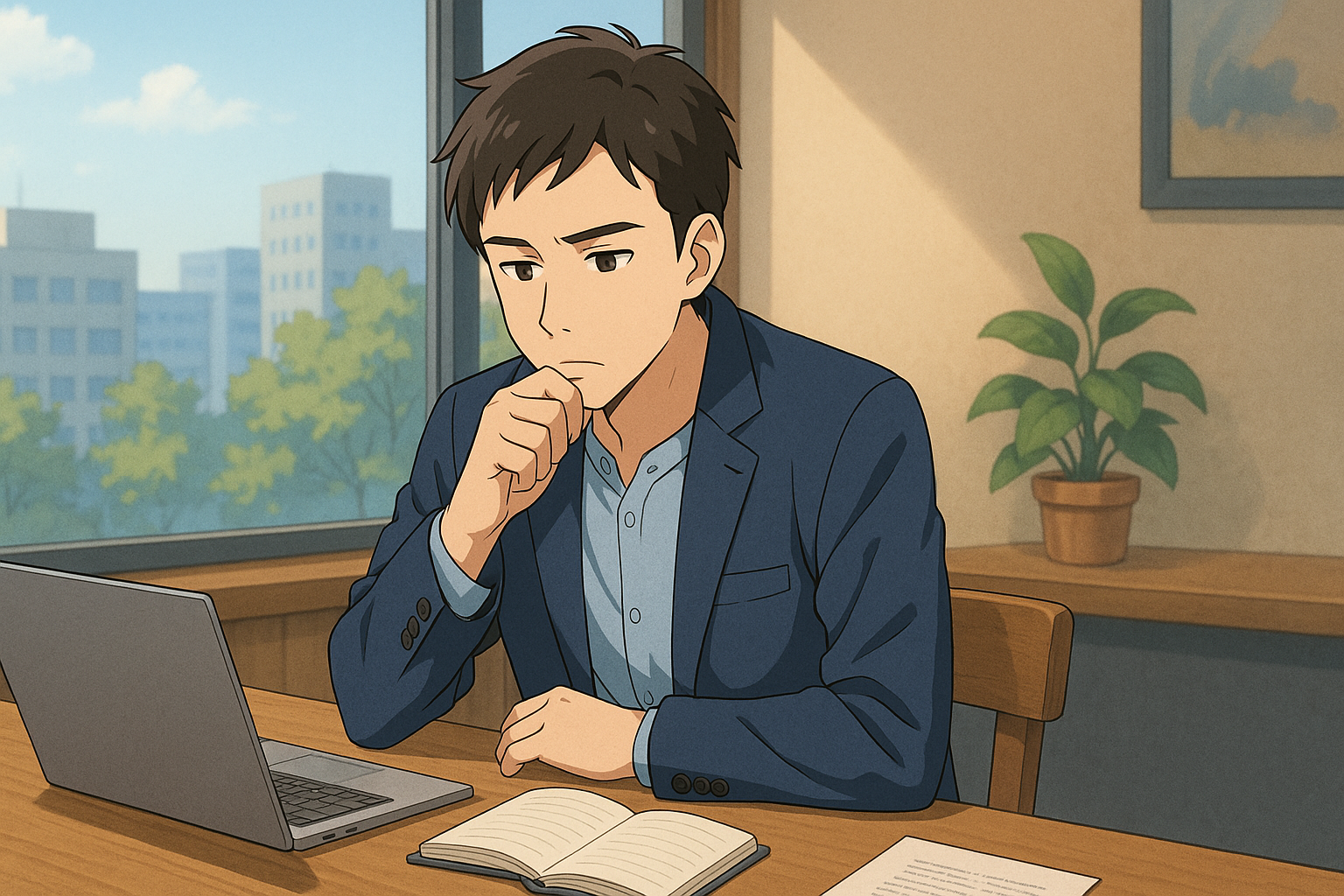


コメント