法人課税部門に配属されて2年目。職員としては3年目の夏を迎えていました。
新事務年度、私は前事務年度と同じ部門に留任となりました。異動の引継ぎ作業もなく、少しだけ人事異動のざわめきを他人事のように眺めていた記憶があります。
とはいえ、同じ部門とはいっても顔ぶれは一変。前年の先輩方は異動となり、代わりに新たなメンバーが加わりました。さらに、1期下の後輩も配属され、自然と「自分が引っ張る側」に回る場面も増えていきました。
局係長明けの統括官
この年、部門の新しい統括官として着任されたのは、主務課で係長を務めた直後の、いわゆる一選抜の方でした。年齢こそ私よりずっと上でしたが、おそらく今でも現役で仕事をされており、職員人生も残すところあと数年──最後はどこかの税務署で署長として締めくくられるのだろうと思います。まさか私の方が先に退職することになるとは……。
統括官の仕事ぶりは、厳しさと寛容さのバランスが絶妙でした。「時に厳しく、時に面白く」。まさに昭和と平成のはざまを行くようなタイプの方で、不正を見つけた夜には飲みに連れて行ってくださるような、今では少し時代にそぐわない“アツい”上司でした。けれど、私にとっては理想的な統括官の一人でした。
自分の「調査スタイル」が見えてきた?
調査2年目になると、前年のような初々しい緊張感が少しずつ薄れ、その代わりに「自分なりの型」のようなものが見え始めてきます。とはいえ、慢心するにはまだ早い年次ですから、「型」といっても、せいぜい“基礎の所作”といった程度だったかもしれません。
この年は特に調査件数が多く、5月初旬の時点で仕掛中の案件が11件。これはさすがに自分でも少し焦りました。法人1統括からも「本当に終わらせられるのか?」と心配されましたが、最終的にはすべてを引継ぎなしで処理しきることができました。
今思えば、あの時期は自分が最も成長していた1年だったように思います。
後輩を連れての実地調査
1期下の後輩と一緒に調査に行くことも多くなりました。とはいえ、私自身もまだ2年目。余裕があるわけでもなく、「少しだけ経験した者」として案内役をこなすのが精一杯でした。ただ、現場に出てしまえばそうも言っていられません。調査の組み立て方、質問の投げ方、帳簿の見方──何もかもが“やってみせる”側に回ることで、その難しさを実感しました。
5月には、「この中から事案を選んでいいよ」と統括官から言われ、自分で選定した法人を自ら調査し、最終的に重加算税の賦課決定まで至った事案もありました。「調査対象をどう選ぶか」「どこに着目するか」など、一連の流れを最初から最後まで通しで経験できたのは、非常に大きな学びでした。
管外出張など
この年は、東京国税局の管外への出張も多く、反面調査や資料収集でいろいろな地域に出向くことがありました。泊まりでの出張も経験し、現地での仕事が終わったあとの夜には、一緒に来てくださった上席が下戸だったこともあり、ホテルの部屋で別れてから一人で近所のバーへ出かけたりしていました。
完全にイキってた調査2年目。今思えばちょっと背伸びしていたのかもしれませんが、そんな時間も含めて、この年は本当に充実していたと思います。
成長を実感した1年
この3年目の1年間は、間違いなく自分が一段上のステージに上がったと感じた年でした。「このままこの道を進めば、税務の専門家としてやっていける」。そんな実感を得たのも、たぶんこの時期だったと思います。
次回は、法人課税部門での3年目と、専科研修について振り返る予定です。同じ部署に配属されていても、年次とともに見える景色は変わっていきます。そんな「同じ場所の違う風景」について、引き続き書いていけたらと思います。
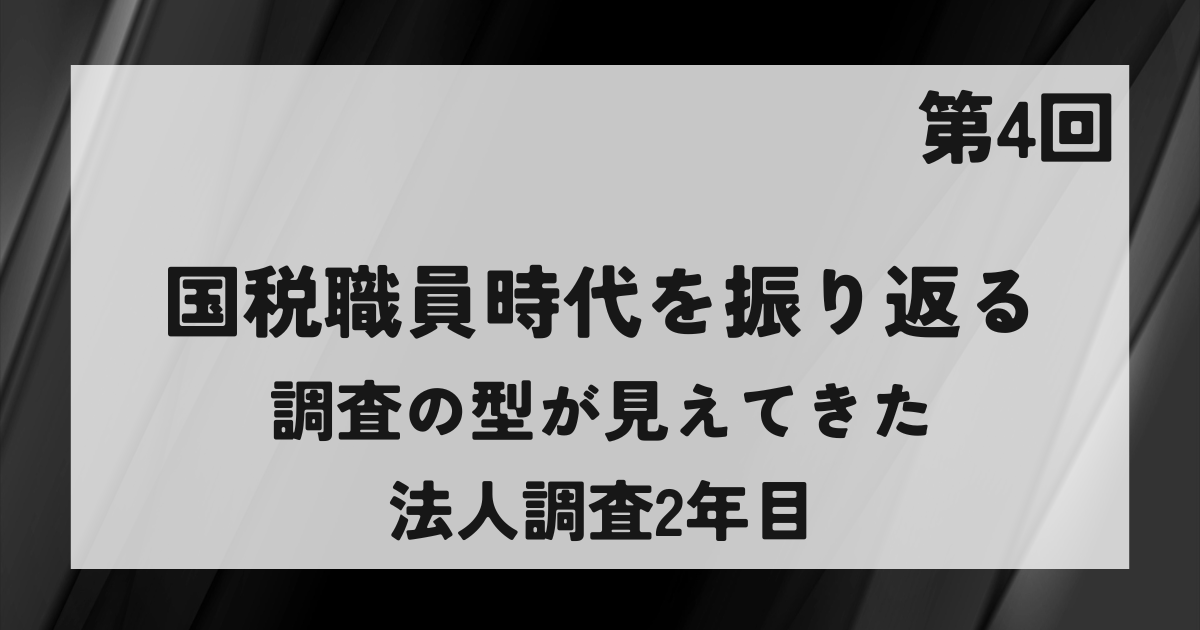
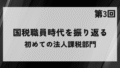
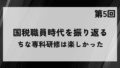
コメント