入庁して5年目。専科研修を終えて初めての異動は、振り出し署から隣接する郊外の署でした。23区に隣接する中規模の署で、通勤経路もほぼ変わらず。地理的な変化は少なかったのですが、仕事の内容は大きく変わりました。
法人調査を希望していた私に下ったのは「法人審理」への辞令。審理といえば、調査担当時代にお世話になった存在であり、まさか自分がその立場になるとは思ってもみませんでした。内示の翌日、前任署の統括官(もともと審理畑の方)から「審理に推したの俺だから!頑張って!」と電話をもらい、返事の代わりに苦笑いしたのを覚えています。
法人課税第1部門での新しい役割
配属先は法人課税第1部門。1~2年目の職員のほか、上席が3人(うち1人は審理上席)という体制で、審理系統に強い法人1統括のもと、新体制がスタートしました。
調査時代は「外に出て納税者に直接向き合う」のが仕事の中心でしたが、審理は全く別物。外部の納税者や調査部門の担当者から寄せられる質問に法令面からアドバイスしたり、調査の審理を行ったりします。
調査と審理、どちらが大変かとよく聞かれますが、単純比較はできません。調査のように現場で即座の判断やスピード感が求められるわけではないので、審理はじっくりと取り組める分、深い理解が必要になります。プレッシャーは納税者からというより、むしろ調査担当者から感じることが多かったです。「あの案件、審理的にいけるのか、ダメなのか?」と問われるたび、こちらも背筋が伸びました。
専科研修の知識が点から線に変わる
審理の仕事を始めてすぐに実感したのは、専科研修で学んだ座学が実務とリンクする感覚でした。法人税法や措置法の条文知識が、現場の事例とつながっていく。「ああ、あのときのあの話は、こう使うのか」という気づきの連続で、知識が点から線に変わった1年でした。
ただ、調査経験は2年半ほどしかありません。それなのに調査担当者にアドバイスをする立場になったのですから、内心は、「こんな俺が偉そうに講釈垂れていいのかしら」と自分にツッコミを入れたくなることもしばしば。だからこそ、役回りとしては調査担当者の背中を押す審理を心がけましたし、ダメなものは上席や担当統括官に対しても遠慮なく「ダメ」と言えるよう努めました。
審理上席と法人1統括に恵まれた日々
この1年は、人間関係にも非常に恵まれました。ペアの審理上席は私より9期上の先輩で、調査部の経験もある頼れる存在。仕事の面倒を見てもらいながら、飲みに誘ってもらうことも多く、サシ飲みでは調査部の話や組織全体の話をたくさん聞かせていただきました。この時間が何より勉強になりました。
法人1統括も素晴らしい方で、部門全体の雰囲気がとてもよかったです。以前別の記事で書いた「もっと褒めた方がいい」という話は、この法人1統括と審理上席からの影響が大きいのです。
参考記事:もっと褒めたほうがいい
部門内の仲の良さを象徴する出来事としては、私の誕生日の日に副署長が不在だったことをいいことに、副署長室でサプライズケーキが振る舞われたことがありました。私の下の名前に「ちゃん」付けされたハート型のチョコレートプレートが添えられていて、恥ずかしさもありましたが、やはり嬉しかったです。事務年度の終わりにあたる5月、私は28歳になりました。
郊外署の「おっとりとした納税者」に驚く
この署の管内は、土地柄もあるのか、納税者の方が非常におっとりしていました。振り出し署では調査先や確定申告会場で罵声を浴びた経験もありましたが、ここではそんなことは皆無。「少し場所が変わるだけで、ここまで違うものなのか」と感動したのを覚えています。人の性質や雰囲気の違いを肌で感じたのも、この年の大きな学びでした。
充実感のある1年、そしてまさかの異動
こうして法人審理という慣れない仕事をしつつも、この1年は非常に充実していました。知識と経験の幅が一気に広がり、成長を実感できた年でもあります。
だからこそ、私はこの署での留任を希望しました。しかし法人1統括からは「調査部を希望しなさい」との助言。もともと調査部で審理担当主査をされていた統括の言葉は重く、希望調べには調査部と記しました。
そして7月に異動内示が下ります。まさかの調査部、東京局調査第一部調査審理課。正直びっくりしましたが、「名前がカッコいい部署だし、同期で誰も行ったことがない。これは俺しかいない」という妙な矜持と誇りも湧いてきました。
異動先は築地に移転する前の大手町合同庁舎、最後の年。次回はこの調査部時代の話をお伝えしたいと思います。
この年の振り返り
この5年目の1年は、仕事の幅が広がっただけでなく、人との関係性が自分を大きく成長させてくれた年でした。調査経験しかなかった私が審理の立場に立ったことで、国税の仕事の全体像がクリアになった感覚があります。
次回は「調査部での新たな挑戦」についてお届けします。異動内示を受けたときの、あの独特な緊張感と期待感を今でも鮮明に覚えています。

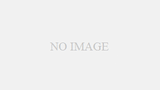
コメント