入庁して7年目。ブログタイトルに「やんちゃ」と自分で書くことにはいささか抵抗があるものの、そんな1年だったのは事実かもしれません。私はこの年、希望していた金融部門――調査第26部門へ異動となりました。配属先は、外に出る調査担当ではなく、内部事務を担う内担でした。
「金融ってなんかカッコいいから」。異動希望の理由はそんな単純なものでしたが、当時の私の胸の内は本当にそんなノリだったのです。
所掌法人数にビビる
配属初日にまず驚いたのは、担当する法人の多さでした。所掌法人数が非常に多く、最初の1〜2ヶ月は右も左も分からず、ひたすら「残業すれば何とかなる」という、今となっては反面教師的な働き方でしのいでいました。
幸いなことに、前任の内担の方が隣の席にいらっしゃり、わからないことはすぐに聞ける環境だったのは本当にありがたかったです。おそらくその方がいなければ、私の内担ライフはだいぶ辛いものになっていたと思います。
内担経験は宝
調査部に異動する際には、「最初に内担を経験すべきか、それともいきなり調査に出るべきか」という議論がありますが、圧倒的に内担経験はしておくべきと個人的には思っています。
内担は縁の下の力持ちで、原則として自ら調査に出ることはありません(もっとも、私は当時の総括主査に連れられて、4件ほど調査に同行させてもらいました)。しかしその分、調査部門全体のスケジュール感や、1年間を通して何をどう進めていくかといった業務の流れを体系的に学ぶことができます。これは後々、調査担当にまわってからも大いに役立ちました。
指示命令系統が明瞭
調査部に来てもうひとつ感じたのは、マニュアルや指示文書の整備が非常に行き届いていたことです。
「この業務は調査管理課のこの指示文書に基づき、〇月〇日までに△△係へこういう連絡をしてください」といった具合に、やるべきことと期限、連絡先が明確に記されています。
さらに、部の総務係からも「この報告様式で提出してください」「こういう集計をお願いします」といったメールが定期的に届きます。それらをもとに業務スケジュールを逆算して組み立てていけば、自然とやるべきことが見えてくる。そういった意味でも、私は非常に仕事がしやすいと感じていました。
内担会など
また、内担には横のつながりの文化がありました。同じ部内の内担同士で内担会と呼ばれる懇親会を開催しており、年に4回ほど、部長・次長・総務・管理企画の方々を招いて飲み会を開いていました。
今もこの文化が残っているかは分かりませんが、当時は同年代か、少し年上の先輩が多く、私はとても可愛がっていただきました。
金曜日の夜、いわゆる“華金”は飲みに出て、その流れで新木場のクラブAGEHAへ行くこともありました。今でこそ閉館してしまいましたが、当時はまだ営業しており、若さゆえのエネルギーで朝まで遊んでいた記憶があります。
29歳にもなってクラブでオールというのは、今振り返ると少々痛々しい気もしますが、若さゆえの勢いだったということでご容赦ください。
金融部門の個性派ぞろい
調査第26部門の構成員もまた、個性豊かな方々ばかりでした。
長年金融プロパーとして調査に携わってきた方、調査審理を極めたベテラン、デリバティブに詳しい若手など、何かに特化した人材が集まり、部門としての地力をひしひしと感じました。
私はといえば、そんな優秀な調査担当者たちの裏側で、更正の請求や調査省略案件の処理、各種書類の整備など、目立たないけれど確実に必要な業務をこなしていました。まさに縁の下の力持ちという言葉を支えに、自分の存在意義を確認していたように思います。
初の部門旅行とブレグジット
この年、初めて泊まりがけの部門旅行にも参加しました。行き先は栃木県の鬼怒川温泉、宿泊先は「あさやホテル」。料理も温泉もすばらしく、いつかまた訪れたいと思える宿でした。
ところでこの旅行、ちょうどイギリスでEU離脱を問う国民投票の開票日と重なっていました。行きの特急スペーシアの中で「英国がEUを離脱するらしい」とスマホで速報を見たのを覚えています。
温泉旅館とブレグジットがセットで記憶に残っているというのも、なかなか貴重な体験です。
まさかの内示
こうして1年間、内担として充実した日々を送り、「来年も調査第26部門に留任だろう」と疑いもしなかった私に、まさかの内示が出ました。
「次は、調査審理課で審理担当をやってもらう」
えっ、内担を1年やって、また調査審理課に戻るの?
そんな異動、前例がないと思っていたのですが、最近ではそういった異動も珍しくないようです。
当時はかなり動揺しましたが、今思えば、必要とされているということだったのかもしれません。時代が変わったのか、単なる偶然か、真相はわかりません。
次回は、調査審理課の審理担当としての1年間をお届けします。プレッシャーもありましたが、得るものも大きかった1年でした。
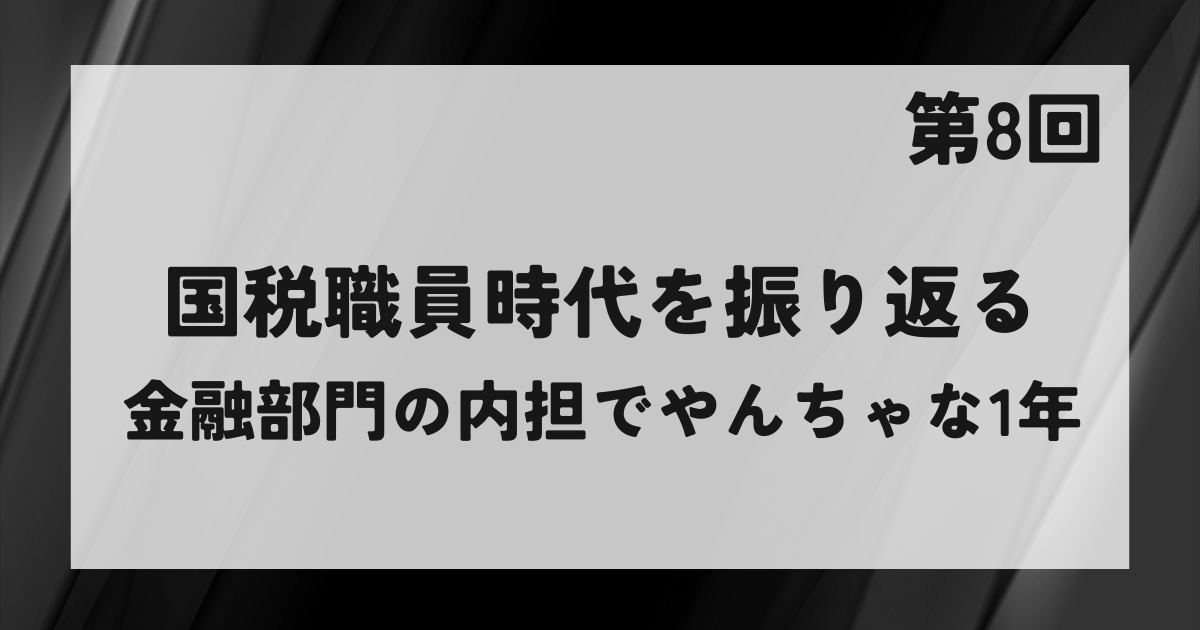

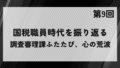
コメント