私はまたしても調査審理課に戻ってくることになりました。最初の調査審理課配属は2年前、総務係としての勤務でした。その後、調査第3部調査第26部門で内担を経験し、再び調査審理課へ。いわば“ただいま”という状態です。
同じ課とはいえ、当時からメンバーはあまり変わっておらず、2年前の面々に「あれ?もう戻ってきたの?」と迎えられたのが妙に印象に残っています。調査部門や課税部に異動して2年くらいして戻ってくる職員も多いため、おかえり感が漂うのはやはり調査審理課特有の空気なのかもしれません。
調査審理課に伝わる1,000日修行
かつて(今も?)、「調査審理課は1,000日修行の場」と言われていた時代がありました。1,000日、つまりおおむね3年間を修行に捧げてようやく一人前の調査審理課の職員であると。もちろん都市伝説的な表現ではありますが、確かに調査審理については仕事の性質上、何か答えが決められているものではないため、最初の1年では“なにがわからないのかもわからない”状態が続きます。
私自身はというと……自信をもって「修行完了」とはとても言えません。むしろ、「3年以上経ってもまだ半人前」のまま抜けきれなかった気すらしています。ただし、これは謙遜ではなく正直な自己評価です。もちろん、期間に比例して実力がつくわけでもありません。勘の良い職員であれば、2年でも十分に立派な元調査審理課経験者として胸を張れるようになる。要は量と質、そして姿勢の問題なのだと思います。
調査審理課って、そもそも何をするのか
調査審理課の仕事は、ざっくり言うと「調査部の調査部門から上がってきた決議書を、法令や証拠に基づいて検討し、適正かどうかを判断する」というものです。前事務の内担時代は、私自身が調査官として決議書を発議する側でしたが、その経験はほんの数件。そんな私がいきなり審理する側に立って大丈夫なのかと、不安は拭えませんでした。
今もそうかもしれませんが、審理担当者2人1組のペアにして、わからないことはベテランの先輩に聞けるようにするという運用でした。私のペアは5期上の先輩。”調査審理課職員に対しては”とても穏やかな方で、私の稚拙な質問にも真摯に向き合ってくださいました。
とはいえ、調査経験が浅くても「これは明らかに証拠資料が足りないのでは?」という違和感を覚える場面は多々ありました。その直感を大切にしつつ、法令を確認し、付箋を貼付して調査部門に返戻する日々。最初は時間をかけながらでも、1件ずつ丁寧に審理していくことで、徐々に手応えが出てきました。
ちなみに、調査審理課の職員はみなさん中央経済社の黄色い表紙の法人税法規集を手に取っていて、図解シリーズに頼らない姿勢が暗黙の文化のように根づいていました。私もその流れに倣い、可能な限り条文にあたるクセをつけるように心がけました。
付箋を貼って黄色マーカー(カッコ書き部分はオレンジマーカー)でマーキングし、決議書を確認しつつポチを打つ。デジタル全盛の令和の世において、アナログかつ泥臭い作業ですが、こうした地味な積み重ねが今の自分に繋がっているのではないかとも思います。
プライベート、絶不調
ここまで仕事のことをやや誇張気味に書いてきましたが、実のところこの年は人生でも稀に見る病み期でした。
専科研修時代から長く付き合っていた女性と別れることとなり、同棲も解消。一人暮らしに戻った私は、どこかで空虚さを埋めたかったのでしょう。仕事帰りに飲み屋に寄ってはしご酒をし、平日深夜まで飲み歩く日々を送っていました。健康的にも、精神的にも褒められたものではなかったと今なら思います。
ただ、そんな日々の中で、後に私の人生に大きな影響を与える人物とも出会いました。それについては別記事で紹介していますので、よければご覧ください。
参考記事:バーで隣に座っていた人
もう少し真面目にやれていたら…
下期に入ると、調査の繁忙期に突入します。私も審理件数をある程度こなすようにはなっていましたが、それでも仕事にフルコミットというよりは、日々をなんとなくこなす感覚が強かったです。もし、このときもっと真剣に仕事と向き合っていたら、人間としても成長できたのではないか。そんな“たられば”を今でも少しだけ抱えています。
事務年度末、隣の係へ
事務年度末、私は同じ調査審理課内で係異動となりました。次の担当は連結(現在で言うグループ通算制度)担当です。
メンバーは、これまでの係員と係長がそのままごそっと隣の係に異動しただけという“引っ越し”的な人事だったため、顔ぶれはほとんど変わりませんでした。「連結ってなんか難しそう」という漠然としたイメージだけを抱きつつ、新事務年度を迎えることになります。
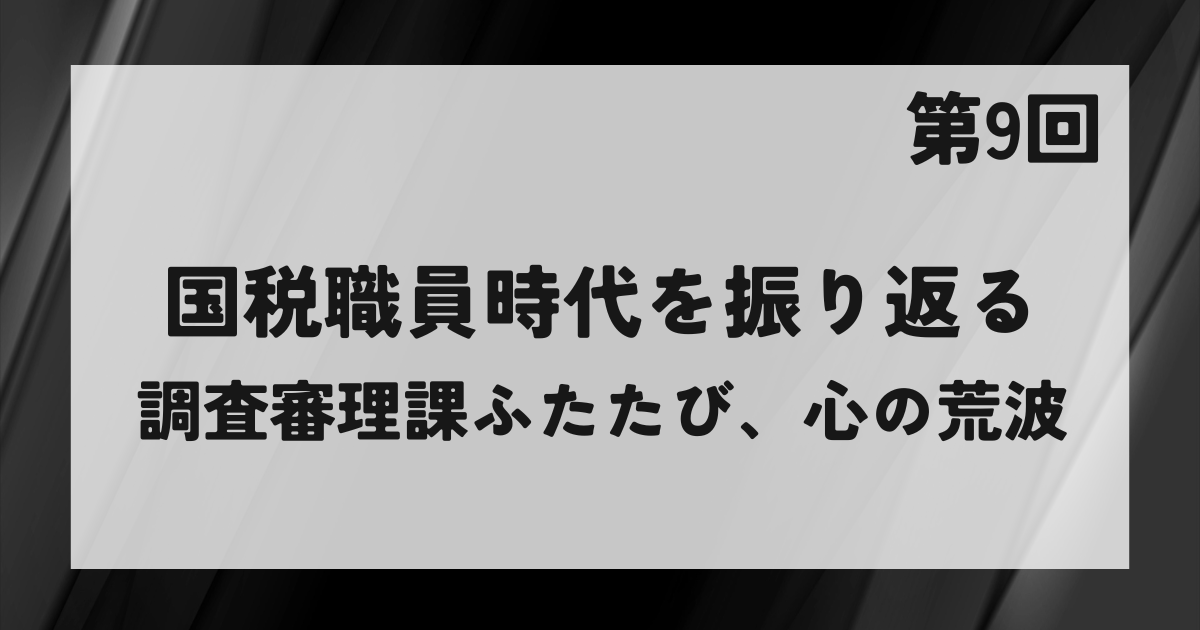
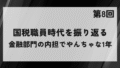
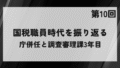
コメント