令和3事務年度、この年も引き続き国税庁の同じ部署で勤務していました。世の中はまだ新型コロナウイルス禍のまっただなか。
第四回の緊急事態宣言が2021年7月12日から9月30日まで、まん延防止等重点措置が4月5日から9月30日、そして翌年1月9日から3月21日まで続きました。外ではマスク姿が当たり前で、オリンピックも無観客開催。職場でも世間でも、時間がどこかゆっくり流れているようで、しかし仕事は待ってくれない一年でした。
国税庁にもリモートの波
この頃、国税庁でもようやくリモートワークがしやすい環境が整ってきました。事務年度の途中からは、自宅から庁内システムへ直接アクセスできるようになり、さらに仕事用の携帯番号も付与。これによって、在宅勤務でもほぼ出社と同じ動き方ができるようになりました。
ZoomやTeamsでのミーティングや課長説明も日常の一部となり、国税の職場の中でもDXがかなり進んだ実感がありました。以前なら、会議室を押さえて書類を配布し…という段取りが必要でしたが、画面共有ひとつで全国の職員と同じ資料を見ながら話せる。時代の変化を肌で感じました。
申告書別表や新設届出書作成の裏側
私の担当は、Q&Aの改訂や、税務申告ソフトウェアベンダー向けの法人税申告書別表のイメージ作成、新制度に伴う新設届出書・申請書のひな型作成、さらには各国税局のワークフロー(事務運営指針や事務提要)改訂と多岐にわたりました。
中でも印象的だったのは、申告書別表のイメージを早期にシステムベンダーへ共有したこと。担当の方から「これで開発が進みます、本当に助かります」と直接感謝の言葉をもらったときは嬉しかったです。庁の仕事は外部からのフィードバックが得にくく、成果物が直接感謝される機会は多くありません。だからこそ、この時の手応えは特に心に残りました。
妻と図書館での勉強の日々
仕事以外では、私生活にも大きな変化がありました。結婚した妻は会計士受験生で、結婚後も近所の図書館でひたすら勉強を続けていました。その姿に影響を受け、「じゃあ私も一緒に勉強しよう」と思い立ったのです。
最初はFP1級の学科試験を独学で勉強し、令和3年5月に受験。合格できそうな手応えを感じると、「税理士試験も独学で行けるのでは?」と欲が出てきました。残り時間的に2科目は難しいと判断し、財務諸表論1科目に絞って出願。理論問題が半分を占め、通勤時間を暗記に充てられるのが決め手でした。
勉強は、朝から図書館に行き、昼は図書館近くの飲食店…のはずが、食べすぎて午後の集中力が削られるという失敗を繰り返し、やがてコンビニで軽食を買って公園で食べるスタイルに落ち着きました。冬には雪景色、春には桜と、季節ごとに表情を変える公園で昼を過ごす時間は、勉強の合間のささやかな癒しでした。
模試の現実と本番の手応え
試験直前は大原もTACも模試の順位は上位70%ほどで、数字だけ見れば合格にはほど遠い位置。しかし諦めずに勉強を続け、試験当日は休暇を申請して臨みました。私の居た庁の部署では比較的夏の時期に休みが取りやすく、この点は本当に助かりました。
試験後に自己採点した結果は、ボーダーと確実の間くらい。結果は合格で、しかも独学・短期間・庁勤務という条件下での達成だったため、大きな自信につながりました。ただし翌年、簿記論に独学で挑んで不合格になるのですが、その話はまた別の回で。
庁勤務にも慣れ、自ら選んだ留任
仕事面では、庁の業務サイクルにも慣れ、令和3事務年度を大きなトラブルなく終えることができました。2年半の経験を経て、自分なりのやり方で業務を回せる感覚も芽生えてきました。
事務年度末のヒアリングでは「引き続き庁に居たいか」と上司に問われ、私は留任を希望しました。理由は、今のプロジェクトチームを離れてもきっとやっていけるという手応えと、庁という職場環境自体に悪くない印象を持っていたからです。
そして令和4事務年度、庁の法人課税課・審理係の実査官に。国税庁の主務課、それも審理係というのは責任も重く、正直なところ「私に務まるのか」という不安はありました。しかし、この1年間が国税職員として最も成長を感じる時間になったような気がします。
続きは次回、第15回でお話しします。
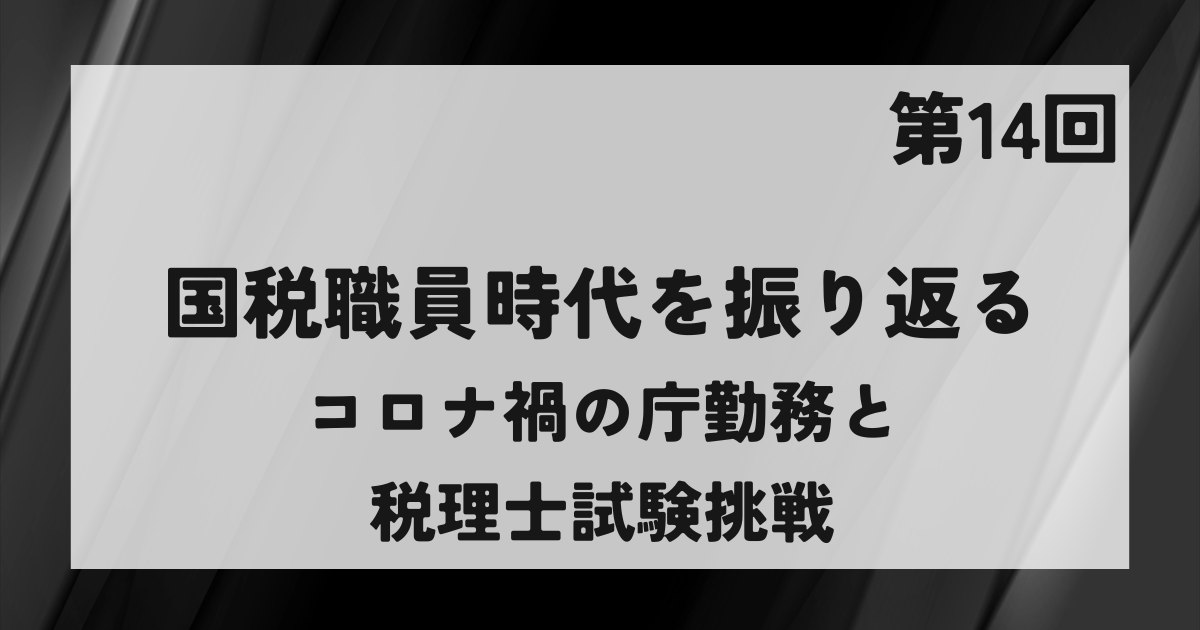
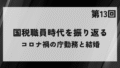
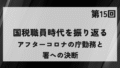
コメント