令和5事務年度、私は東京局の、いわゆる五大署の一つで審理上席となり、法人会担当に就くことになりました。
署勤務なんて本当に久しぶりで、正直ちょっとワクワクしていました。しかも8月には税理士試験が控えていたので、「最初は勉強時間を確保しつつ、ゆったり過ごせたらな…」なんて淡い期待を抱いていたのです。
しかし、その期待はあっという間に粉々に。
異動時というのは「どういう案件が、どういう理由で越年しているのか」まできっちり引き継がれるものだと思っていました。ところが署の内部事務は違いました。細かい引継ぎはほぼなく、「とりあえずやってみて」スタイル。見よう見まねで日々を回すうち、「これはまずいな」と感じ、後任にはしっかり引継書を残すことを心に誓いました。
引き継ぎ不足と電話地獄の洗礼
7月は、慣れない仕事と、前任がある程度片付けておくはずだった案件のダブルパンチで、忙殺の日々。さらに追い打ちをかけたのが、納税者からの電話でした。内容の難易度が高い上に、頻繁にかかってくるためタスクが何度も中断。しかも電話交換手さんが慣れていないせいか、「とりあえず法人ならこの人に」という振り分けが横行し、「この質問、そもそも国税じゃない…」と思う案件まで私の電話にかかって来ました。
この電話対応こそ、一番堪えました。庁勤務時代のように腰を据えて資料と向き合える時間はなく、常に呼び出しベルが鳴る環境。今思えば、集中力が削られる最大の要因でした。
勉強との二重生活
そんな中でも、仕事終わりには署近くの大原自習室へ直行。20時までには退庁し、21時半まで勉強して帰る日々を続けました。
直前期は、答練を細切れにして回す方法を実践。60分の第3問を解いて答え合わせする日、30分問題を2題やってまた答え合わせをする日、このような日々を繰り返し、想定の8割の時間で上位3割に入れる点数にまで仕上げました。1日90分の勉強時間でも、工夫次第で仕上げられることを実感しました。
そして迎えた8月の試験当日、有給をしれっと取得して簿記論にリベンジ。去年より手応えは感じつつも、自己採点はボーダーギリギリ。落ち着かないまま11月まで過ごすことになりました。結果的には合格でき、同時に税理士試験の免除申請も済ませられたので、心穏やかな年末年始を迎えることができました。ちなみにこの年末年始、久々に妻とのんびり食事に出かけたり、社会保険労務士の勉強を始めたりしました(後にあっさり断念するのですが…)。
法人会担当という独特の仕事
法人会担当の仕事は、なかなか独特です。会員企業向けに説明会を開き、理事会や総会では署長や幹部のアテンド、挨拶文の作成も担当します。ロジ周りの調整は法人会担当ならではの業務で、夜の会合にも官費で出席し、意見交換を行うことも。お酒が好きな人なら楽しめる役回りかもしれません。
私もお酒は好きなので、幹部のお世話を除けば夜の会合はそれなりに楽しみました。民間企業の方と顔をつなげる機会も多く、独立後の人脈作りという意味でも、非常に良いポジションだったように思えます。
若手職員との距離感
署には若手職員が多く、飲み会や雑談の場では彼らの話を聞くのが楽しい時間でした。アラフォーが若手の飲み会で目立っても仕方ないので、基本的に口は出さず、お金だけはちゃんと出すスタイル。とはいえ、時には恋愛相談まで受けることもあり、「いや、同年代に聞いたほうが…」と思いながらも、つい真剣に答えてしまう自分がいました。異動期には「調査部に行きたいのですが、話を聞かせてください」と相談されることも多く、今のXの質問箱と同じようなやりとりをリアルでしていた感じです。
署はこんなもんかと思った瞬間
下半期になると、17時ダッシュで帰れるほど仕事にも慣れてきました。しかし同時に、「署はこんなもんか」という感覚が芽生えます。
庁ほどDXが進んでおらず、自分の振り出し署で使用していたシステムが現役稼働中。時代錯誤な働き方の中では、成長の手応えを感じにくいと悟りました。令和6事務年度の異動希望は、庁の審理室を希望しました。法人課税課以外の経験を積みつつ、自分の審理経験を活かせる場だと思ったからです。
しかし結果は留任。担当統括官も「なんでだろうな」と首をかしげる展開でした。「ああ、もう庁にとって私は不要な存在なんだな」と少しおセンチな気分になりつつも、辞めるという選択肢を頭の片隅に置き、次の人生のプランをぼんやりと考え始めました。
次回はいよいよ、このシリーズの最終回。私の国税職員としてのラストイヤーです。
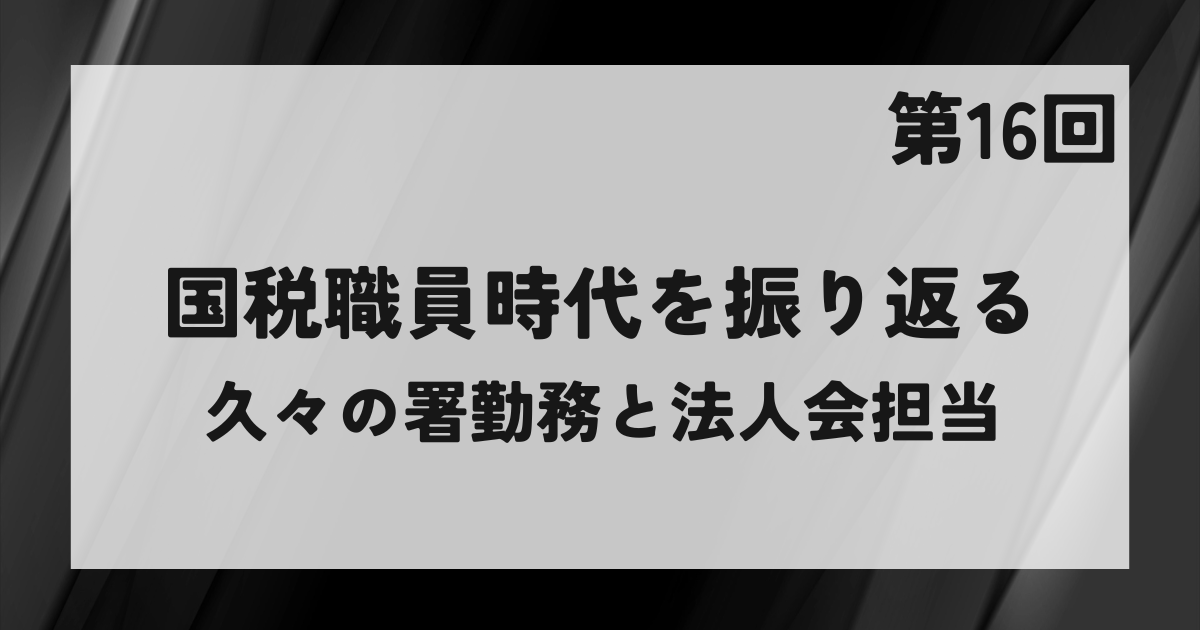

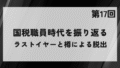
コメント