最近『みぃちゃんと山田さん』を読みはじめました。少し歪んだ親子関係といった日常的な場面が淡々と描かれています。しかし、読み進めるうちに「家が安心できる場所ではない」という構図が浮かび上がってきます。
この点で本作は『タコピーの原罪』を思い出させます。どちらの作品でも、家庭が「回復の場」として機能していません。登場人物たちは外で傷つき、家に帰っても癒やされず、むしろ追い詰められていきます。親という存在は保護者ではなく、圧力や不安の源に近い立ち位置にあります。
ハッピー道具が鈍器に変わる時代
『タコピーの原罪』はしばしば『ドラえもん』のオマージュとして語られます。ハッピー星から来たタコピーが道具を使ってしずかちゃんを笑顔にしようとする構図は、のび太に手を差し伸べるドラえもんと似ています。しかし結果はまったく異なります。ハッピーをもたらすはずの道具が、暴力や絶望の引き金として描かれるのです。
昭和の『ドラえもん』では、しずかちゃんの家庭は理想的な「よい家」の象徴でした。父母の愛情に恵まれ、安定した家庭環境のもとで暮らしている。のび太が外で叱られても、家に帰れば夕食があり、優しい両親が存在し、ドラえもんが慰めてくれる。家庭は「HPを回復できる場所」でした。
一方で、令和の作品ではその回復機能が失われています。『タコピーの原罪』の登場人物たちは、家に帰っても癒されるどころか、さらに傷ついていきます。『みぃちゃんと山田さん』でも同様に、笑顔をつくるための関係性が、かえって人を痛めつけてしまう構図が見られます。幸福を求めた手段が、いつのまにか鈍器のように変質している。この皮肉こそ、令和の作品が持つ特徴のひとつだと感じます。
平成に残っていた救済の構造
平成の『まじかる☆タルるートくん』は、『ドラえもん』のアンチテーゼとして描いた側面があると作者の江川達也氏は言及していました。主人公・江戸城本丸は、タルるートの魔法で楽に解決するのではなく、努力や根性で困難を乗り越えていきます。家庭には温かさがあり、父親は息子の失敗を受け止め、再挑戦を促してくれる。家庭が主人公を支える基盤として描かれていました。
この時代の物語には、「努力すれば報われる」「家族に支えられて成長できる」という構造がまだ残っていました。家は安全地帯であり、そこで心を癒し、再び外の世界へ向かう力を得ることができたのです。
しかし令和の物語では、そうした救済の構造が崩れています。努力しても報われず、母の優しさは存在せず、家に帰っても安らげない。家族という制度が、癒しの源からストレスの発生源へと変わってしまったように見えます。
父の威厳から母の圧力へ
かつての物語では、「父と息子の確執」が主題となることが多くありました。『美味しんぼ』の海原雄山と山岡士郎、『エヴァンゲリオン』の碇ゲンドウとシンジなど、巨大な父性とそれに反発する子の構図は定番でした。
しかし現代では、父の存在感そのものが薄れています。サラリーマン家庭というのが一般化し、家業を継ぐという構造が崩れ、「父から子へ継がせるもの」がなくなった。その結果、母の存在が肥大化しました。母は過保護でありながら支配的で、愛情と支配が区別されにくい。『みぃちゃんと山田さん』の登場人物にも、そうした歪んだ親子の近さが見られます。物理的には同じ家にいても、心の距離は遠く、互いに監視し合っているような関係です。
令和的家族観の変遷を感じた
『みぃちゃんと山田さん』や『タコピーの原罪』は、個々の家庭の悲劇を描いた作品というより、時代の変化を映した鏡のように感じます。家庭が機能不全に陥ることが珍しくなくなり、外でも内でも癒されない社会。安心できる場所が消えたとき、人は「ハッピー道具」を手にしても幸福にはなれないのかもしれません。
昭和は理想的家庭の時代、平成は努力と愛情の時代、令和は喪失と再構築の時代です。親子の断絶はもはや特殊なテーマではなく、社会全体の共通言語になりつつあります。
そう考えると、『みぃちゃんと山田さん』という作品の背後には、確かに令和的家族観の変遷が映し出されているように思います。

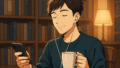

コメント