アンミカさんの有名な一言です。もはや「〇〇って〇〇あんねん。」というネットミームと化してはいますが、これは単なる色彩の話ではないと思い始めてきました。
新しい挑戦と「言語運用能力」
新しいことに挑戦しようとするとき、人には大きく二種類の反応があると思います。
「面白そうだ、やってみよう」と肯定的にとらえる人と、「失敗したらどうしよう」と不安で足がすくむ人。この両者の違いは言語運用能力の低さという観点で説明が可能かと思います。ちなみに、言語運用能力という言葉は、橘玲さんの書籍『朝日ぎらい』という言葉から定義を引用しています。
言葉の数が少ないと、不安の正体を細かく描けず、漠然としたモヤモヤのまま立ち止まってしまうのです。
国税の現場と解像度の差
国税の職場でも、この言葉の解像度の差を実感する場面が多々ありました。上司は限られた時間の中で「こういう方向で進めよう」と抽象的に示すしかない場面が多いのです。新人に対して箸の上げ下ろしまで細かく指導する余裕はありません。
例えば「調査の決議書を期日までに内部担当に回付しなさい」という指示。表面だけ見れば「書類を作って回せばいい」と思うかもしれません。実際には、その決議書は調査先から修正申告書をもらわなければ完成しません。そして修正申告書は、相手方が税務当局の指摘事項に納得したうえで、調査先や代理人から提出されるものです。
この前提を理解していないと、何から手をつけていいのかわからず混乱します。かなり極端な例ではありますが、言葉と知識の不足が原因で、見ている世界が粗いままなのです。
「白」と「緑」に宿る民族的な言葉の力
ここで再びアンミカさんの「白って200色あんねん」に戻りましょう。
多くの日本人にとって「白は白」です。しかし、イヌイットの人々にとっては雪や氷の微妙な違いを見分けることが生死に直結するため、数多くの「白」の言葉を持っているといわれます。言葉が多いほど、世界を細かく切り分けて認識できるのです。
日本人も緑のバリエーションには強いですね。若草色、萌黄色、深緑…。山や田畑に囲まれた生活が長かったからでしょうか。言葉が多いからこそ、景色を細やかにとらえられるのです。逆に言葉が少ないと「ただの緑」としか見えず、世界はのっぺりとしたものになってしまいます。
ゼロ百vsグラデーション
同じ場所に立っていても、言葉を持つ人と持たない人では見える世界がまるで違います。言葉はレンズの解像度のようなものです。
私自身、日々ブログを書くときには、なるべく自分なりの言葉を掘り出して伝えようと思っています。そうすることで、読者の方にも世界の見え方が変わる瞬間を共有できたらいいなと思うからです。
横断歩道を渡るとき
例えば、横断歩道を渡るとき。右から来る車と左から来る車を確認するのは当たり前ですが、言語運用能力が高ければ「もしかすると信号を無視する自転車が突っ込んでくるかもしれない」といったシナリオまで想像できます。こうして視界に入る情報を細やかに言葉にできる人は、不安に過剰にとらわれず現実的な行動がとれるのです。
一方、言葉のストックが少ない人は「車が来るかも」という曖昧な不安だけで足を止めてしまうかもしれません。不安を消すには、解像度を上げて「何が危険で、どう対処するのか」を言葉で整理する必要があるのです。
言葉で世界を拡張する習慣
では、どうすれば言語運用能力を高められるのか。私が思うに、一番の方法は紙の日記を書くことだと思っています。誰にも見せない紙の上で、自分の考えを言葉にしていく。これが世界を言葉で掘っていく訓練になります。
SNSでのアウトプットは他人の目を意識してしまいますが、日記帳なら気兼ねなく書けます。さらに読書も重要です。娯楽小説でも構いません。大量の語彙を取り込むことで、自分の世界を拡張できる気がします。
不安を言葉にできる人は、不安の原因を特定し対策を立てられる。結果、不安はただの「課題」に変わります。これが「漠然とした不安」と「具体的な問題」の違いです。
補助輪を外す
私自身も、言語化の鍛錬をしてきたおかげで、自転車の補助輪を外すように少しずつ不安を乗り越えてこれた気がします。もちろん、まだまだ解像度の粗い部分は多いですが、「白って200色あんねん」という言葉の通り、世界にはまだ見えていない色がたくさんある。
その色を一つずつ言葉にしていく訓練として、Xで寄せられた質問に対して、なるべく肌触りのある言葉で回答をしているつもりではあります。

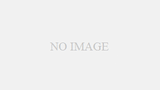
コメント