「自分の時間単価を考えて行動しよう」とよく言われます。
頭ではわかっていても、なかなか実践できないのが人間の性ですね。私もその一人です。長らく公務員をやってきたので、いわゆる「サラリーマン思考」というか、「自分の時間=タダ」という感覚が染み付いてしまっています。給与は毎月一定額振り込まれるわけで、極端に言えば成果や効率にかかわらず生活できてしまう。そんな環境で過ごすと、時間単価なんて概念とは縁遠くなるのも当然かもしれません。
独立を控えた今はそうはいきません。成果を出さなければ報酬は入ってこないし、行動一つひとつにコスト意識を持たざるを得ません。いまさらながら、「自分はタダじゃない」と痛感しています。
青春18きっぷで大阪へ
時間単価を考えずに行動した例として思い出すのが、30代になってからの大阪旅行です。学生のころに戻ったような気分で「青春18きっぷ」を握りしめ、在来線を乗り継いで片道8時間近くかけて行きました。お金を節約したかったのだと思います。現地で友人に会ったとき、「学生みたいなことしよるな~」と笑われました。確かに、新幹線ならあっという間に到着して、現地での時間をもっと楽しめたはずです。今考えれば、浮いたお金以上に失った時間のほうが大きかったのではないでしょうか。
この経験は、私にとって「安さを取るか、時間を取るか」という典型例でした。当時は迷わず前者を選んでいましたが、独立を考えるようになった今なら、きっと違う判断をすると思います。
家事を外注する発想
時間単価を意識するうえで最も身近なのは家事かもしれません。私は独身時代からPanasonicのドラム式洗濯乾燥機を導入しています。洗剤の自動投入機能付きで、これが非常に良かったです。日々、洗剤を量って入れるという小さな作業から解放されると、意外なほどストレスが減るのです。積み重ねると大きな差になります。
さらに食洗機も導入しました。食後に食器を洗う時間が不要になるのはもちろんのこと、シンクに食器がたまって「やらなきゃ」という心理的な負担も減りました。こうした機械への投資は、時間単価を高める大きな武器だと思います。
ただし、私の課題はここからです。ドラム式や食洗機のように「一度買えば自動でやってくれる」ものにはすぐ投資するのに、買い物や掃除、調理のように「人に外注できる」領域には妙な抵抗感があります。気がつけばスーパーであれこれ迷って1時間、帰宅してからも料理に時間をかけすぎて、その日の自由時間がほとんどなくなった…そんな日もあります。時短家電には寛容なのに、人の手を借りることには急に財布の紐が固くなる。自分でも不思議です。
公務員と独立のちがい
こうした「時間はタダ」という感覚が強く残っていたのは、公務員時代の働き方が影響しています。サラリーマンは、成果に対して直接給料が支払われるわけではありません。例えば、有給休暇を25日余らせて一気に使っても、その1か月間は成果ゼロでも給料は振り込まれます。当たり前のようでいて、実は特殊な世界です。
独立すれば当然ながらそうはいきません。働かなければ売上はゼロ。時給換算どころか「ゼロ円」という現実が目の前にあります。私も退職後に「これは意識を変えなければ」と実感しました。稼ぎ始める前から「脱・時給思考」を意識して行動していかないと、いつまでたっても自分を安売りすることになってしまいます。
自分はタダじゃない
時間単価を意識するというのは、必ずしも「すべての行動をお金換算で判断しろ」という話ではありません。気分転換や趣味であれば、時間をかけること自体に意味があります。ただし「自分の時間はタダじゃない」という意識を持っているかどうかで、選択の質は大きく変わります。
私の場合、青春18きっぷの旅行やスーパーでの買い物に時間を費やすこと自体が悪かったわけではありません。ただ、それを無意識にやってしまうのか、意識的にやっているのか。この差が大きいのだと思います。
自分の時間単価を意識することは「自分の人生をどう過ごすか」を選び取る作業にほかなりません。今後は、「自分はタダじゃない」という気持ちを持ちながら、日々意思決定していきたいとは思っています。実践が難しいですね。

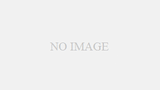
コメント