公務員として働いていたとき、耳にタコができるほど聞かされた言葉があります。それが「ワークライフバランス」です。今では民間企業でも当たり前のように使われている言葉ですが、私にとっては強烈な違和感が残る言葉でした。
国税職員時代、総務課や全体研修の場で、定期的に「ワークライフバランスを意識していきましょう」と発信されていました。直接上司から「バランスを取れ」と押しつけられたことはありませんが、発信側も「上から言わされている」ような雰囲気が漂っていました。正直、本気で理想を描いている人は誰もいないのでは、と思ったのです。
憲章の理想と現実
もともと「ワークライフバランス」という概念は、内閣府の男女共同参画局が提唱したもので、憲章には次のように書かれています。
誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、今こそ、社会全体で仕事と生活の双方の調和の実現を希求していかなければならない。
なるほど、立派な理念です。「仕事と生活の調和」そのものには共感しますし、家庭や介護に忙殺される人を支える仕組みは必要だと思います。そこに異論はありません。
ただ、私が引っかかったのは「バランス」という言葉そのものです。バランスと聞くと、どうしても「仕事5:生活5に分けましょう」というような“均等割り算”のイメージがつきまといます。まるで人生の総量が100しかないかのように扱われるのが、どうにも腑に落ちませんでした。
人生は算数ではない
実際には、仕事に10全振りしたい時期だってあるはずです。たとえば若い独身のころ、全力で働いて実力をつけたい人に「いやいや、生活にもちゃんと5割振りなさい」と言うのは、どこかズレています。逆に、家庭や育児に全力を注ぎたい人に「仕事とのバランスを」と言ってしまうのも、本人にとっては余計なお世話です。
人生は算数ではありません。
10をどう割るかではなく、仕事も生活も、それぞれ10にできるよう努力するほうが前向きではないでしょうか。
公務員時代の「バランス」
私の職場では「毎週水曜日は定時退庁日です」と繰り返しアナウンスされていました。確かに一部の職員にとっては救いになったと思います。しかし、繁忙期の調査や事務作業に追われているときに「今日は定時だから帰りましょう」と言われても、心が休まらない人もいたのではないでしょうか。
その姿を見ながら、私は「バランスを外から決められても意味がない」と感じていました。バランスを取るとは、他人から言われて従うものではなく、自分で選び取るものだと思うのです。
独立という選択
そんな違和感を抱えながら働き続け、最終的に私は税理士として独立する道を選びました。もちろん、独立すれば自由と同時に責任も大きくなります。しかし、働きたいフェーズでは思い切り働けますし、生活を優先したい時期にはそちらにシフトすることもできます。
独立したからといって、仕事と生活が自動的に調和するわけではありません。ただ、少なくとも「水曜日は定時退庁だから帰りましょう」と言われることはありません。働くか休むかを自分で決められることこそ、私にとっての「理想のワークライフ」なのです。
言葉より大事なもの
振り返ると、私の違和感は「ワークライフバランス」という言葉の枠に押し込められることにありました。バランスを外から測られるのではなく、自分で調整できる幅が広がることが大事です。
これから税理士として活動していく中で、仕事も生活も10:10にできるような日々を目指したいと思っています。もちろん、仕事が取れないフェーズもあるでしょうし、仕事に忙殺されるフェーズもあるでしょう。それでも、自分で選び取れるという感覚があれば、不思議と前向きに取り組める気がします。

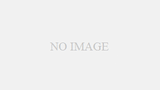
コメント