洋書を翻訳した本を読んでいると、苦手なパートが出てきます。だいたい「誰々の場合」という実例が延々と続くところです。ノースカロライナ州に住むAさんがどうで、6歳の頃からこうで、18歳でこうなって……という類の描写です。情報量はあるのに、読書のテンポが落ちます。
この種のパートは、1回目は基本的に流し読みしてきました。悪い言い方をすると「話が長い」と感じてしまうからです。主張が知りたいのであって、人物の履歴を追いたいわけではない。
ただ、最近気づいたのは、再読のときにそこをじっくり読むと、意外と学びが多いということです。1回目の自分が拾えなかったものが、2回目では拾うと結構刺さることが書いてあったりします。
何読もすると新たな味わいがある本はいいですよね
自分の読書スタイルは、目次を見て、読みたいところから読みます。最後まで読むことを至上命題にしません。必要なところを先に取りにいく。
この読み方をしていると、著者が言いたいこと、骨格となる主張は、前半に詰まっていることが多いと感じます。もちろん例外はありますが、多くの本では、序盤で問題提起と結論の方向性を示し、中盤以降で根拠や実例を厚くしていきます。
だから1読目は、ザッと読んで、大まかな主張と構造を理解しようとしています。「誰々の場合」を飛ばすのも、怠けというよりは、主張をいち早く掴むための作戦に近いと思います。先に全体像を把握してから、必要なら細部に戻る。その順番のほうが、読み手の負荷が小さいです。でも神は細部に宿るとも言ったもので、その細部が後々に面白く感じられることもあるから不思議です。
再読で実例が面白くなるのは「見る目が変わる」から
例えば、1読目の自分は「結局何が言いたいのか」を探しているので、実例を読んでも「で、結論は?」となりがちです。ところが2読目は、結論がすでに頭にあります。すると実例は、「この主張は、どういう場面で当てはまって、どういう場面で当てはまらないのか」を見せる素材に成り得ます。
ここが面白いところです。実例は、著者の都合の良い話を並べているだけにも見えますが、丁寧に読むとむしろ逆で、例外や揺れも含んでいることがあります。人間の話なので、きれいに当てはまらない部分が出る。その「当てはまらなさ」が、主張の限界や使いどころを教えてくれます。
自分はここで初めて、「あの長い人物紹介にも意味があるのかもしれない」と思いました。居住地や年代の情報は、単なる飾りではなく、背景として効いている場合があるからです。生活環境や文化圏が違うと、同じ行動でも意味が変わることがあります。そこまで読み取れれば、実例はだいぶ立体的になります。
「二度以上読む前提」の書籍
ここまで考えると、本は1回で終わらせるより、二度以上読む前提で向き合ったほうが楽だと思えてきます。1読目で主張を掴む。2読目で実例などを細かく拾う。この二段構えにすると、「あの長い人物紹介」を無理に飲み込む必要がなくなります。
翻訳本の後半に出てくる「アリゾナ州の誰々の場合」は、1回目の自分はたいていの場合読み飛ばしてしまいますが、2回目の自分には、主張を現実に接続する材料として見えてくることがあります。本を二度三度読むと視点が変わる、というのはこういうところに出るのだと思いました。
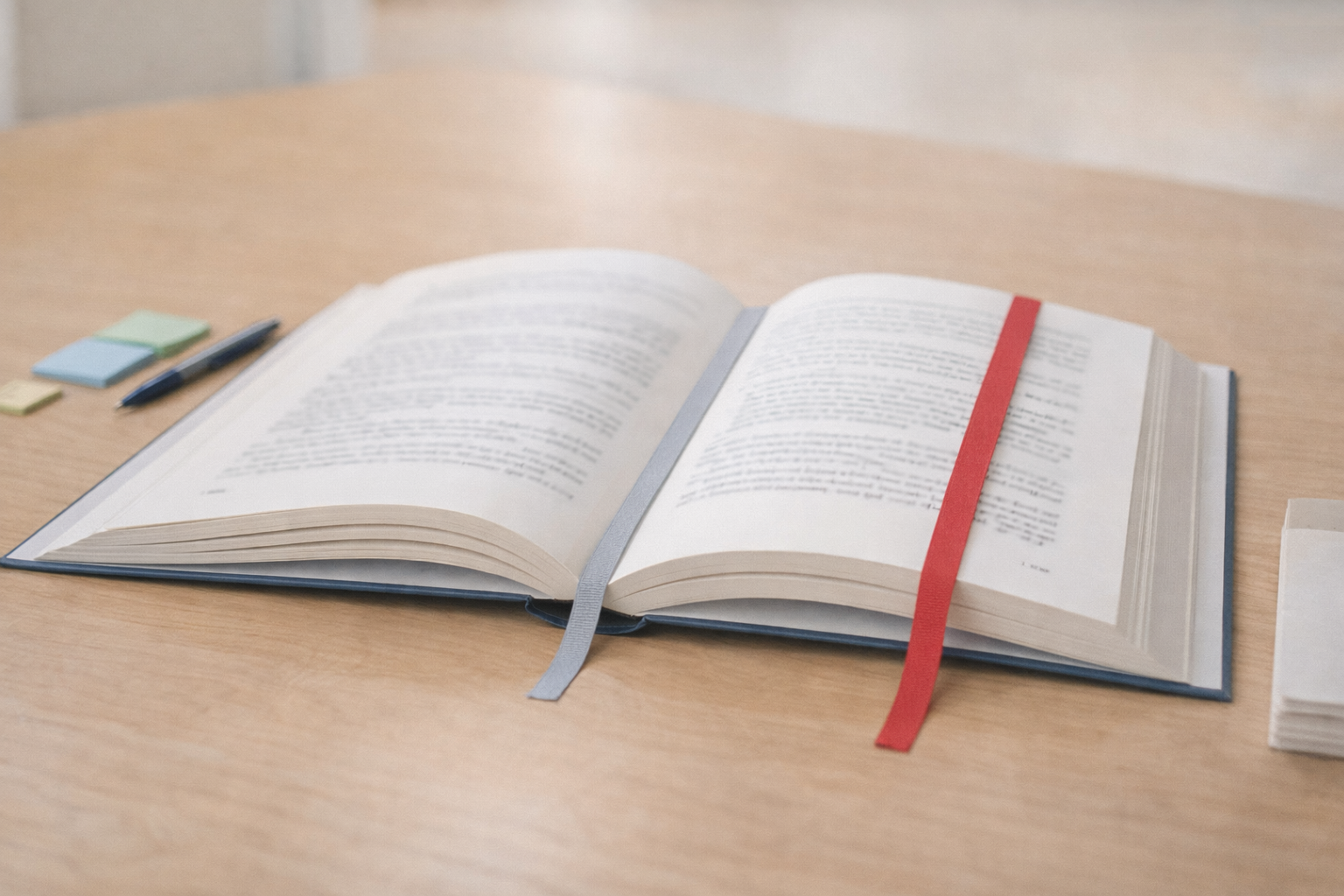

コメント